平成15年6月5日現在における我が国の世帯総数は4580万世帯となっている。 世帯構造別にみると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1490万世帯(全世帯の32.5%)で最も多く、次いで「単独世帯」1067万3千世帯(同23.3%)、「夫婦のみの世帯」978万1千世帯(同21.4%)の順となっている。 世帯類型別にみると、「高齢者世帯」は725万世帯(全世帯の15.8%)、「母子世帯」は56万9千世帯(同1.2%)となっている。
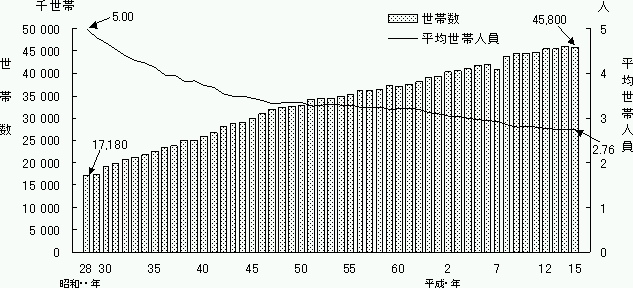
(出典:厚生労働省)
|
Personnel Management Office Report 6月号 発行日:平成16年6月1日 |
| 永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)人事労務の担当者の皆さんにつきましては、労度保険の更新手続が完了しほっとしていることと思います。一方、社会保険の算定基礎届の提出がすぐ始ります。
さて、国会では、まだ、年金改正について色々場外乱闘が続いています。「未加入」と「未払い(未納付)」の違いについて、いままで、曖昧に使っていた一部マスコミもここ数ヶ月間の学習効果のためか徐々に注意深く使うようになってきました。江角マキコさんの問題について、当初、朝日新聞は、「未加入」と書いてきましたが、正しくは、強制加入期間に支払わなかったので「未払い」である訳ですね。
|
最近のニュースから |
過労死認定は157人 03年度の厚労省まとめ
働き過ぎが原因で脳・心臓疾患になり、2003年度に労災認定を受けた人が312人で、うち過労死は157人に上ったことが25日、厚生労働省のまとめで分かった。いずれも前年度に比べ微減した。
一方、過労による精神障害や自殺で認定された人は108人で、過去最多となった。
厚労省によると、脳・心臓疾患の申請は、前年度より114人減り705人となった。しかし、、認定は過去最多の前年度より5人減っただけで、依然として深刻な状況が続いている。
認定者のうち、男性は297人で、女性は15人。年代別では50代、職種別では運輸・通信従事が最も多かった。
一方、うつ病などの精神障害になったり、精神疾病を患い自殺を図ったりしたとして申請した人は、前年度より97人増え、過去最多の438人。このうち、未遂を含む自殺の申請は121人で、40人が認定された。(共同通信 5月25日)
発足する労働審判制度
労働審判法が12日に公布され、2年以内に「労働審判制度」が発足することになった。言うまでもなくこの制度は、解雇・配転や賃金、あるいは女性の処遇・セクハラ問題などをめぐって、個々の労働者と雇い主との間のもめごと、いわゆる個別労働紛争が急増している最近の状況に対応したものである。
個別労働紛争の増加は、経済環境の変化に対応するために、企業が成果主義賃金に象徴されるような人事労務管理の個別化を進めているなど、日本の企業文化の変化が背景にある。それを受けて、労働者意識、雇用形態も多様化し、さらに、労働市場にも変化が及んでいることも指摘できよう。
とはいえ、それにしても個別労働紛争の増加はすさまじい。全国の労働相談コーナーに持ち込まれた相談が、昨年度73万4,000件にも上った。そのうち解雇、労働条件引き下げなど、民事上の個別労働紛争が14万件もあり、前年度よりも36.5%も増加した。さらに、このうち、都道府県労働局長による助言・指導に回されたのが4,377件(前年比87.7%増)、紛争調停委員会によるあっせんは5,352件(前年比76.3%増)と、たいへんな急増である。
労働審判制度は全国の地方裁判所に置かれ、職業裁判官である労働審判官1人と、労働関係に関する専門的経験を持つ労働審判員2人により、紛争当事者片方の申し出で審判手続きが行われる。当事者双方の合意による調停が成立しない場合は、審判を下すことになる。審判に異議が申し立てられなければ、審判は裁判上の和解と同一の効果を持つ。異議がでた場合は、裁判所に訴えの提訴がなされたとみなされ、正式の裁判に移行する。審理は3回以内で終わらせることとしているので、3ヶ月程度で決着を見るはず。これにより、労働紛争に最も求められるスピードと実効性の担保も期待される。
発足してまだ年月の浅い都道府県労働局長による紛争解決制度との関係など、やや疑問点はあるものの、まずは欧州諸国にある紛争処理システムに一歩近づいたことは間違いない。(JIL 5月)
| 今月の統計 |
| 世帯構造及び世帯類型の状況 | |||
| 平成15年6月5日現在における我が国の世帯総数は4580万世帯となっている。 世帯構造別にみると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1490万世帯(全世帯の32.5%)で最も多く、次いで「単独世帯」1067万3千世帯(同23.3%)、「夫婦のみの世帯」978万1千世帯(同21.4%)の順となっている。 世帯類型別にみると、「高齢者世帯」は725万世帯(全世帯の15.8%)、「母子世帯」は56万9千世帯(同1.2%)となっている。 |
|||
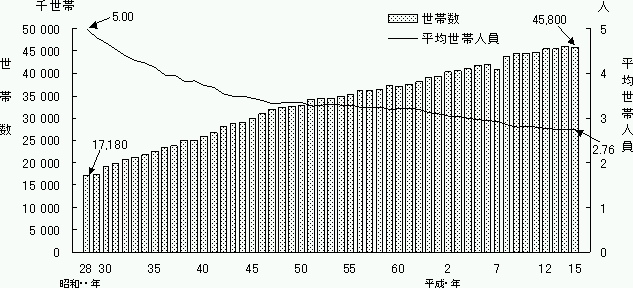
(出典:厚生労働省) |
|||
| 今月の判例 |
安川電機のパート解雇無効 「選定基準に合理性なし」
共同通信によると、大手産業機械メーカー「安川電機」(北九州市)によるパート女性従業員二人の解雇の有効性が争われた訴訟で、福岡地裁小倉支部の川久保政徳裁判長は11日、対象者を選ぶ基準に合理性がなかったとして、解雇は違法で無効との判決を言い渡した。
訴えていたのは、いずれも北九州市のパート女性従業員。川久保裁判長は、慰謝料50万円と解雇以降、月額約10万円の賃金を2人に支払うよう会社側に命じた。
判決で川久保裁判長は受注減少による人員削減の必要性は認めたものの、2人の解雇で抑制される経費はわずかと指摘。
上司が単独で短期間にまとめた報告で2人が解雇対象に選ばれ、評価基準が、ほかの従業員とは異なるなど恣意(しい)的な面があったとした。
判決によると、原告2人は安川電機の工場で部品取り付け作業をしていた。3カ月ごとのパート契約をそれぞれ約17年、約14年にわたり更新。会社側は2001年6月、契約期間内だった2人を含む計31人のパート従業員に整理解雇を通告した。
5月11日
(あとがき)
経済統計などで明るい話が徐々に増えてきています。一方、一般市民の感覚では、「これで一息ついた。」と感じる状況にはなっていません。企業のリストラの効果による経済の回復局面であるからであるという説明もよくなされます。今後、国内で所得格差が拡大していくと予想する経済学者の声もめずらしくありません。今後数年間のうちに日本が過去に経験したことのない時代に突入していきそうです。