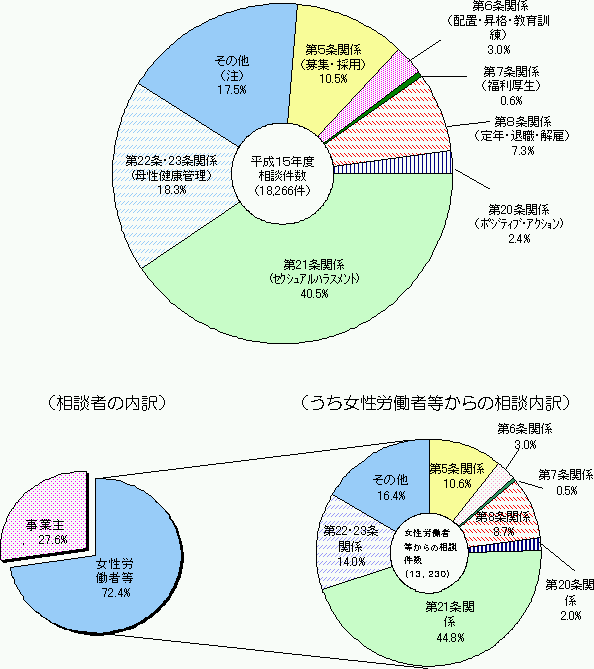|
Personnel Management Office Report
7月号
発行日:平成16年7月1日
|
| 永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)人事労務の担当者の皆さんにつきましては、社会保険の算定基礎届の提出の準備は既に出来ていることと思います。また、源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所につきましては、7月10日の送付期限までの源泉税の準備も出来ていることと思います。
さて、年金改正法案が通過した通常国会(159回)が終了し、参議院選挙に突入します。今回改正された年金関係の法律の内容については、マスコミ等でかなり取り上げていますので、概ねのことはおわかりと思いますが、この通信面においても次回以降解説をして行く積もりです。
サービス残業が1万8千件 03年に労基署が是正指導
時間外労働(残業)に対する割増賃金を支払わないサービス残業があったとして、全国の労働基準監督署が事業主に残業代の支払いを求めた是正指導が、昨年1年間で1万8511件に上ったことが15日、厚生労働省のまとめで分かった。
前年(約1万7077件)を1500件近く上回る6年連続の増加で、過去約30年間で最も多かった。労働基準法違反容疑で書類送検した件数も、前年の49件から84件に増加した。
厚労省の集計によると、労基法や労働安全衛生法の違反を是正するため、2003年は全国の約12万1000の事業所を立ち入り調査。このうち、約15%に当たる事業所で割増賃金が支払われていないことが判明した。
03年には、サービス残業で約65億円の未払い分が発覚した中部電力や、消費者金融最大手の武富士、大手百貨店の松坂屋などが是正指導を受けた。(共同通信)
[6月15日]
公益通報者保護法も成立
企業や行政組織の不正行為を内部告発した従業員らを解雇などの不利益から守る「公益通報者保護法」が十四日の参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。食品の産地偽装、自動車のクレーム隠しなど重大な不祥事が相次いで関係者の告発で発覚したのを受け、政府が今国会に提出した。施行は平成十八年四月以降の見通し。
安易な告発の増加を懸念する自民党や経済界に配慮し、同法では保護対象の条件を厳格化した。このため、消費者団体や専門家からは「かえって告発を抑制する」との批判が出ている。
同法は国民の生命、財産などの保護に関係する法令違反の告発を「公益通報」とみなし、告発者への降格、減給といった扱いを禁止。対象は法令違反が生じるか、「まさに生じようとしている」場合と規定、緊急性の高い内容に限定した。
告発者が外部組織に連絡した場合は、(1)証拠隠滅の恐れがある(2)通報後二十日以内に調査するとの通知がない−など内部への通報より一段と保護のための条件が厳しくなっている。(産経新聞)
[6月15日]
| 男女雇用機会均等法の施行状況 |
|
|
労働局雇用均等室への相談 ―女性労働者等からの相談トップは、セクシュアルハラスメント、増加傾向にある定年・退職・解雇―
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めている。
平成15年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、約1万8,000件、このうち約7割が女性労働者等からの相談であった。
相談内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが約4割と最も多く、次いで母性健康管理に関するものが約2割であった。なお、女性労働者等からの相談のうち、定年・退職・解雇に関するものが1,157件(8.7%)と、昨年の1,038件(8.0%)より増加した。
|
|
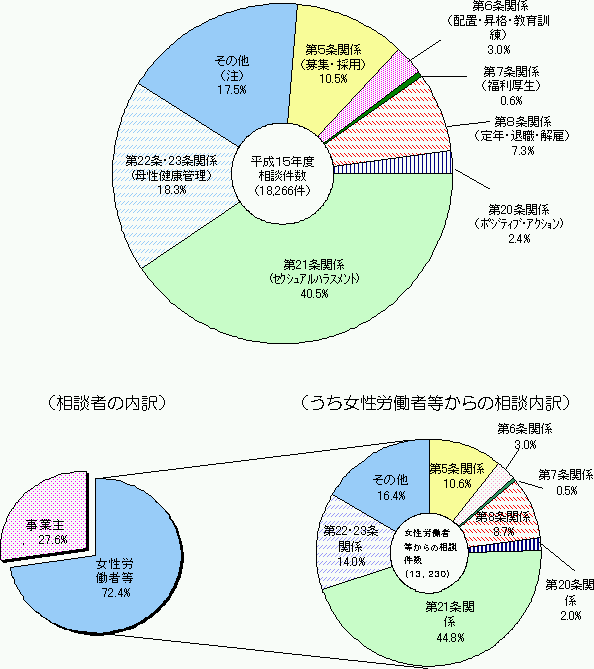
(出典:厚生労働省) |
|
1500万円支払いで和解 住友化学の男女差別訴訟 安易な姿勢に警鐘と女性側
共同通信によると、女性であることを理由に昇進や賃金で差別を受けたとして、大手化学メーカー「住友化学工業」(大阪市)の女性社員ら3人が、会社に同期、同学歴の男性との差額賃金など総額約1億6,000万円の支払いを求めた訴訟は29日、同社が解決金として計1,500万円を支払うことで大阪高裁(市川頼明裁判長)で和解が成立した。
提訴から9年近くを経た決着となり、女性側代理人の弁護士は「同社はコース別の管理を行い転換制度もあるが、外形的に制度を設ければいいという安易な姿勢に警鐘を鳴らすものだ。同様の転換制度を導入している企業は多く、和解の影響は大きい」としている。
住友グループ3社に対する一連の男女差別訴訟で、和解成立は昨年12月の住友電気工業に続いて2件目。住友金属工業については一審大阪地裁での審理が続いている。
訴えていたのは大阪府の石田絹子さん(59)と矢谷康子さん(54)、愛媛県の有森洋子さん(61)=昨年4月に定年退職。
大阪地裁は2001年3月、3人の賃金について「同期、同学歴の男性社員と比べ著しい格差がある」と認めたが「試験などに合格すれば昇進して男性と同じ処遇を得られる機会があった」として請求を棄却していた。
一審判決によると、3人は高校卒業後、1962〜68年に入社。同社は70年に将来の幹部候補の総合職と、補助的業務中心の一般職の2コース制を導入し、総合職への転換制度もできたが3人は一般職のままで昇級などが遅れた。
控訴審では住友電気工業訴訟和解後の今年2月以降、裁判所主導で和解協議が進められた。女性側によると、昇格についても協議したが合意せず、7月に石田さんが定年退職し、矢谷さんが専門職に転換することも踏まえ、解決金支払いを条件とする和解となった。
6月30日
(あとがき)
すでにご存知の方も多いと思いますが、先月(6月)、米サンフランシスコ連邦地裁が,世界最大の小売りチェーン、ウォルマート・ストアーズの女性従業員らが、昇進や給与の面で差別待遇を受けたとして同社を相手に起こした訴訟を、集団訴訟として認める決定を下しました。これにより退職者も含め全米で160万人以上の女性が原告とみなされ、企業に対する人権訴訟では最大規模となるもようです。原告側が勝訴すれば巨額の損害賠償金支払いを迫られるとして、同社の株価が下落したのはいうまでもありません。
実は、このニュースよりもずっと以前からウォルマートでの悪い労務管理・労使関係は、我々労務関係の研究をしている者の間ではしばしば話題になっていました。このような事件に発展するのは時間の問題だったと言えるでしょう。ウォルマートには、労務管理の重要性を真に認識し直して欲しいところです。