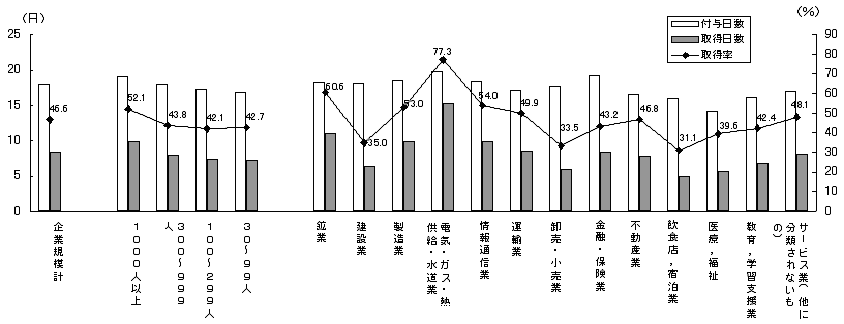|
Personnel
Management Office Report
12月号
発行日:平成17年12月1日 |
| 永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)さて、今年もあとひと月となりました。年末調整などで慌しくなりますね。来年4月施行の高年齢者雇用安定法改正のために、新しい雇用延長制度の作成に追われている方々も多いことと思います。最近、日本IBMとカゴメが、同法改正にあわせた雇用延長制度を発表したので、この紙面にて紹介します。
高年齢者雇用安定法改正、日本アイ・ビー・エムの場合
日本アイ・ビー・エムは、企業競争力の維持と更なる強化を目指し、高い能力を持つ人材が継続して働くことができる雇用制度を拡充する。2006年4月より、単年度契約によって65歳まで勤務できる継続雇用制度を中心に、多様な雇用形態を提供する。退職後の継続雇用制度を拡充し、高い能力を持つ社員には、より長期にわたって雇用の機会を提供することとした。雇用形態の例は、以下のとおり。
[高度専門職]
IBMグローバルに認定された資格を持ち、極めて高い専門性を発揮し続け、貢献度の非常に高い社員は、60歳定年後も高度専門職として、IBM在籍時とほぼ同等の処遇を維持しながら、単年度契約で65歳まで働くことが可能となる。
[ニア・エキスパート]
高い能力を有し、今後も会社への貢献が期待される社員が55歳となった際に選択できる。一度定年扱いで退職した後、新たに単年度の雇用契約をかわし、最大65歳まで働き続けることを可能。長年培った豊富な経験や高い能力をもとに、チームに総合的に貢献する役割を担うと共に、スキルの共有を積極的に行い、後進への指導・育成にも力を入れることを目的とする。
[プロフェッショナルコントラクト(有期雇用契約)/セルフ・エンプロイド(準委任契約)]
コンサルタント職においては、有期雇用契約/準委任契約を選択することが可能。これらの契約形態は目標達成時の報酬額が大きいことが特徴。有期雇用契約は、会社と一定期間の雇用契約を結ぶ(初回は2年または3年、成果に応じ更新。一回につき上限3年、原則1年単位)。従来60歳まであった契約期間の上限を、この度65歳まで延長する。コンサルテーションからシステム構築までのトータルなサービスの提供を自らの裁量で行える、極めて高い能力をもったコンサルタントにおいては、個人事業主として会社と準委任契約を結び、年齢制限無く働くことが可能。
高年齢者雇用安定法改正、カゴメの場合
食品上場企業初、再雇用を65歳まで延長 〜パートタイム勤務からフルタイム勤務での雇用へ変更〜
カゴメ株式会社は、2006年4月1日から定年退職者の再雇用上限を65歳まで引き上る。
2001年4月に導入した再雇用制度で63歳までとしていた上限年齢を2歳延長する。現行制度はパートタイム勤務で年金受給を前提とした制度設計をしているが、2006年4月以降は、年金を前提としないフルタイム勤務に変更する。これにより、パートタイム勤務では活かしきれなかった定年退職者の高いスキルや経験を十分に活用し、働き甲斐をもって65歳まで勤務できるようにする。
制度の変更点について
・ 63歳から65歳まで再雇用制度の期間を延長
・ パートタイム勤務からフルタイム勤務へ変更
・
目標管理制度を再雇用期間も適応し処遇に反映
再雇用制度内容
1. 一般社員と同様のフルタイム勤務
2.
目標管理制度を導入し、賞与および契約更新に反映
3. 一年契約の63歳までの契約が原則ではあるが、成績優秀者は65歳までの延長あり
4.
審査基準
① 職場の規律・調和の遵守性
② 健康
③ 体力
④ 過去3年の人事評価
⑤ パソコン操作能力
「賃金不払残業解消キャンペーン月間」における無料相談ダイヤル(11月23日)の相談受理結果
厚生労働省においては、11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」と定め、賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すための啓発活動を行っており、その一環として、11月23日(水)「勤労感謝の日」に各都道府県労働局において全国一斉の無料相談ダイヤルを開設した。 この無料相談ダイヤルに寄せられた相談の概要は、以下のとおりであった。 厚生労働省としては、今後とも、「賃金不払残業総合対策要綱」に基づき、重点的な監督指導の実施や「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。 なお、相談のあった事案のうち、問題があると認められる事案については、監督指導等により的確に対応していく。
○ 相談の概要(カッコ内は昨年度の件数)
1
相談件数は、全国で1,247件(1,430件)であり、労働者本人からの相談が893件(958件)、労働者の家族からの相談が288件(399件)のほか、使用者からの相談も13件(5件)寄せられた。 また、相談のあった業種としては商業が287件と最も多く、次いで製造業が244件、建設業が112件であった。
2
相談のうち賃金不払残業に関するものは852件(1,053件)であり、時間外労働に対する手当について、一切支払われていないという相談が最も多く371件(442件)であった。 また、相談のうち時間外労働に対する手当の不払いが1箇月100時間以上であるとする相談は103件(144件)であった。
3
なお、労働時間の管理方法については、タイムカード等客観的記録によるものが最も多く341件(401件)であり、次いで自己申告制によるものが203件(244件)であった。
年次有給休暇取得率、0.8%低下(平成16年
年次有給休暇の取得状況
平成16年(又は平成15会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数は除く。)は、労働者1人平均18.0日(前年18.0
日)となっている。そのうち労働者が取得した日数は8.4日(同8.5日)で、取得率は46.6%(同47.4%)となり、前年に比べ0.8ポイント低下した。 産業別にみると、最も取得日数が多く、取得率も高いのは、電気・ガス・熱供給・水道業で15.3日、77.3%となっている。一方、最も取得日数が少なく、取得率も低いのは、飲食店,宿泊業で5.0日、31.1%となっている。
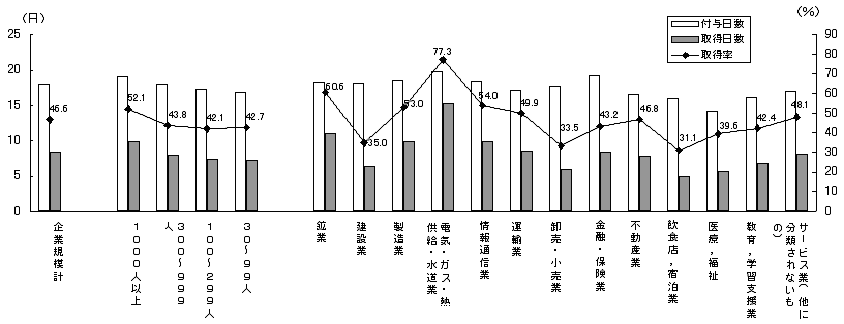
(あとがき) 一級建築士による耐震強度偽造問題が日本中を震撼させています。結果は、関連した個人や企業のほとんどが破産することになりそうです。結局、皆もやっているだろうと大きなリスクを侵して違法に手を染め少々の徳をすることをどう評価するかです。昨日まで大目に見られていた違法が今日から突然厳しい取り締まるを受けることもあります。「どうせ問題にされない違法だから。」と高を括っている所にとんだ落とし穴があります。