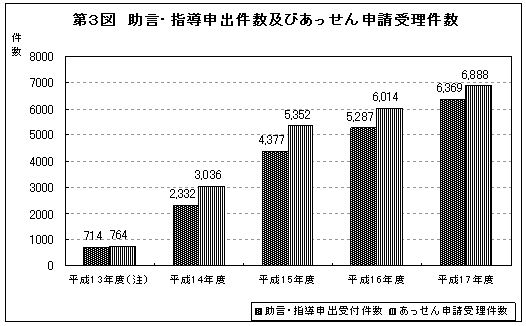
|
Personnel Management Office Report 6月号 発行日:平成18年6月1日 |
| 永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)寒い日と暑い日が交互に入れ替わっている日々が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。労働保険の年度更新の手続きは、恙無く終了したことと思います。住民税の納期の特例を適用されている会社におきましては、6月10日が従業員の住民税の支払い期限となりますから気をつけて下さい。
|
最近のニュースから |
労働審判の申し立て93件 1カ月間の最高裁まとめ
共同通信によると、解雇や賃金不払いなど増加する労働紛争を迅速に解決するため、4月1日に各地裁で始まった労働審判制度への申し立て件数が、1カ月間に全国で
93 件あったことが2日、最高裁のまとめで分かった。
年間の申し立て件数について最高裁は制度づくりの際、1,500
件前後と推定しており、ほぼ想定通りのスタート。解雇をめぐる紛争が中心を占める一方で、賃金や年次有給休暇取得、退職金などの申し立てもあり、多様な紛争を反映した形だ。
最高裁によると、最も多いのが東京地裁の 20件。名古屋、横浜両地裁の7件、大阪地裁の5件と続き、都市部が上位を占めた。全国
50の地裁のうち、31の地裁で申し立てがあり、長野、福井、高松、福岡など
19地裁は申し立てがなかった。 内容の分析はしていないが、東京地裁の場合、20件のうち、解雇無効を求めた地位確認が半数の
10件。これ以外に損害賠償が3件、賃金請求が2件、退職金や解雇予告手当がそれぞれ1件など。
これらの中には、職場で殴られたことを上司に訴えたら逆に解雇された契約社員のケースや、名古屋大病院に非常勤で勤務する医師の契約更新拒否など「非正社員」からの申し立てもあった。
労働審判は、申し立てから 40日以内に第一回期日を設けるため、大型連休明けに実質審理が始まり、6、7月ごろに判断が示されそうだ。
5月 2 日
日本マクドナルドで労組結成/ 200人でスタート
連合は 29日、ハンバーガーチェーン大手の日本マクドナルドに、労組が結成されたとして記者会見を開いた。会見では、「日本マクドナルドユニオン」の栗原弘昭委員長が、「弊社は過去
35年間、社員が一致団結して成長を続けてきたが、近年の売り上げ至上主義、チグハグな経営で長時間労働に陥り、仲間の退職も相次いでいる。現場の窮状に気づいてもらうには、対等な立場で話し合える労組が必要と判断した」などと結成の動機について語った。
「日本マクドナルドユニオン」は 15日に結成され、
29日、会社側に対して結成通知と要求書を提出した。組合員は店長ら約
200人規模での旗揚げとなったが、連合の地方組織である地方連合会を通じて、全国
4,000 店舗に働く最大約 13万人のクルー(パート・アルバイト)に参加を呼びかける勧誘活動もスタートさせた。連合としても、特定企業を対象に組合加入をバックアップするのは初めての試みだ。
結成通知と同時に会社側に手渡した要求書では、(1)
適時、営業方針などを組合に説明する労使協議会を設置すること (2)
店長の長時間労働の実態を調査し、店長職にある者に時間外・深夜・休日労働手当を支給すること (3)
クルーの有給休暇の取得向上のため組合と協議すること――などを求めており、会社側から6月6日までに文書回答を受けることにしている。
日本マクドナルド社は 2004年に、現在の原田泳幸・最高経営責任者(CEO)に交代。以降、
100円マックや早朝・深夜( 24時間)営業の拡大などを進め、売上を伸ばしてきた。しかしこうした中で、昨年
12月には、現職店長が東京地裁に、「マクドナルドの店長は労働基準法の管理監督者に当たらない」として未払残業の請求を求めて提訴。これに対し、会社側は答弁書の中で、全面的に争う姿勢を明らかにしていた。
5 月 31 日
| 今月の統計 |
《平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大
平成17年度の当該制度に係る助言・指導申出件数は6,369件で、平成16年度比20.5%の増加となっている。
あっせん申請受理件数は6,888件、同じく14.5%の増加となっている
このうち、合意が成立したものは2,961件で43.2%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは450件で6.6%、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは3,406件で49.7%となっている。
処理に要した期間は、1ヶ月以内が63.5%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が27.9%となっている。
申請人は、労働者が6,775件で98.4%と大半を占めるが、事業主からの申請も106件で1.5%となっており、労使双方からの申請も7件で0.1%あった。
労働者の就労状況は、正社員が60.0%と最も多いが、パート・アルバイトが16.8%、派遣労働者・期間契約社員も15.9%を占めている。
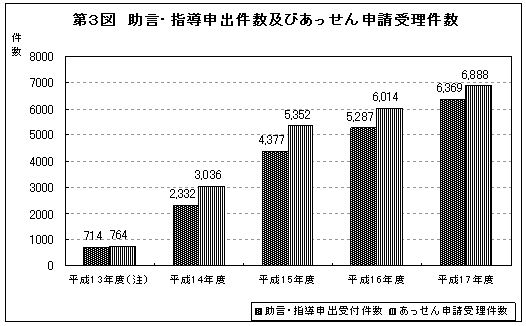
| 今月の司法・行政 |
米州職員の解雇無効 東京地裁、日本法を適用
共同通信によると、米ジョージア州港湾局極東代表部(東京、閉鎖)の元職員小原澄江さん(52)が「契約職員への変更拒否を理由に解雇したのは違法」として、州政府側に解雇無効と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は
18 日、解雇を無効とし、州政府側に未払い賃金約
4,200 万円の支払いを命じた。 州政府側は日本での裁判権免除を主張したが、中西茂裁判長は昨年9月の中間判決で「今回の雇用契約は国家の主権にかかわるものではなく、裁判権は免除されない」として退け、その後は雇用契約の根拠法が日本の法律なのか同州の法律なのかや、解雇当否などが争われた。
中西裁判長はこの日の判決で、採用が日本人によって日本国内で手続きされたことや勤務場所のほか、日本の厚生年金や各保険が適用されたことなどから、契約の根拠法は日本の法律と認定。
その上で「解雇の必要性などを説明した事実は認められず、解雇は乱用というほかない」との判断を示した。
判決によると、小原さんは 1995 年、同極東代表部の現地職員として採用されたが、2000
年9月に解雇された。 5 月 18 日
中部電社員の自殺は労災 上司の指導は不適切と認定
共同通信によると、中部電力の男性社員=当時(36)=がうつ病になり自殺したのは業務が原因として、愛知県内に住む妻(42)が遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の橋本昌純裁判長(永野圧彦裁判長代読)は
17日、労災と認め、処分を取り消した。 橋本裁判長は、長時間労働に加え、上司が勤務中に結婚指輪を外すよう指示したり「心構え」と題する作文を書かせるなどした指導方法が「不適切で、精神的な負担となった」と認定。うつ病の発症と悪化、自殺は業務に起因すると結論付けた。
妻の代理人弁護士は「行政訴訟で上司の指導の在り方を批判した判決は珍しいのではないか」と評価している。
判決によると、環境設備課で勤務していた男性は
1999 年8月、主任に昇進。長時間の勤務や上司の指導が心身の負担となってうつ病になり、同年
11 月に自殺した。 妻は、名古屋南労基署に労災認定を申請したが退けられ、提訴した。
5 月 17 日
(あとがき) 社会保険庁が国民年金の未納問題でまたトラブルを起こしたのはマスコミで取り上げられている通りです。確かに、「国民年金法第90条」では、「該当する被保険者が申請したときは、保険料の納付を要しない」としており、社保庁の職権で適用できるとは書いてないですね。と言うことは、行政上、この免除適用は、違法な又は瑕疵ある行政処分となるのでしょうか。今後を見守りたいと思います。