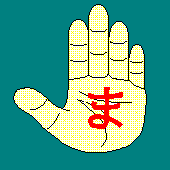Last updated:12/06/2020__v1.2

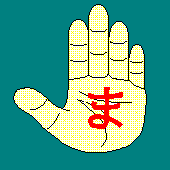
「尺八ホームページ」をお作りになっている立花宏さんから、「作曲のテクニックやMIDIデータを作っている環境や手順など書いたらどうでしょう。」とのご教唆をいただきました。私にはとても作曲のしかたについて書く能力も資格もありませんが、作曲をしてみようと思っていらっしゃる方の何かの参考になればと、曲作りのプロセスをまとめてみました。
- 1.曲作りに必要な素材
- 2.メロディーの記録
- 3.曲の構成
- 4.楽譜を書く
- 5.清書のしかた
- 6.MIDIの入力
1.曲作りに必要な素材
私が曲を作る際、使っているのは次のようなものです。
罫 紙
カード
筆記用具(シャープペンシル、ボールペン、消しゴム、定規)
- (1) 罫 紙
- 「罫紙」はB4サイズのコクヨ「ケイ−10」を使っています。尺八の曲を作る場合、「ロツレチ」で書いたほうが清書のときに便利なので、縦書きができる罫紙を使います。五線紙でもいいのですが、不思議なもので五線紙に面していると洋楽的なメロディーになってしまうことが多いので、もっぱら罫紙を使っています。B4という大きさもちょうどよくて、曲の構成を考えたりするときは、ある程度「見晴らし」がきくほうがいいのです(A4ではちょっと小さい気がします)。
罫紙には、曲の編成に合わせてボールペンで縦に線を引いて使います。三重奏曲なら3行ごとに、四重奏曲なら4行ごとに線を引きます(ただし、四重奏曲の場合は二尺三寸管を使うことが多いので、その場合には5行おきにして、一尺八寸管と二尺三寸管の両方の指使いが書けるようにします)。それから、小節線を横に引いていきます。1行につき5小節つくります。
- (2) カード
- 私の曲づくりは、ほとんど思いつきでやっていますので、いきなり罫紙に向かって書き始めるということはありません。たまたま浮かんできたメロディーをメモしておいて、あとでまとめるときに罫紙を使います。その浮かんできたメロディーを書きとめるのに使っているのが「カード」です。カードもいろいろなサイズが文具店に並んでいますが、ほどほどの大きさがあり携帯にかさばらないものを選ぶのがいいでしょう。私が使っているのは、「LIFE情報カードA6横罫(7mm)」です。
- (3) 筆記用具
- 筆記用具は特別なものはありません。定規は、罫紙に線を引くために使いますので、30〜40cmくらいの長さがあるものを用意します。
戻る
2.メロディーの記録
- (1) 思いつきのメロディー
- 皆さんは、どういうわけかメロディーが浮かんでくる経験をお持ちではないでしょうか? そういうメロディーをカードに書きとめておいて、あとで曲にまとめていきます。大事なことは、思いついたメロディーをその場で書きとめることです。そうでないと、すぐに忘れてしまいます。
- (2) カードへの記入
- カードに書きとめる際、私は「ロツレチ」で書いていきます。これは五線紙に書くよりもはるかに便利で、自宅であろうと会社であろうと電車の中であろうと歩きながらであろうと、場所を選びません。小節線などもあまり気にしないで書いていきます。
- (3) カードの管理
- このようにして書きとめたカードがだんだんたまってくると、その中から気に入ったものをピックアップして、曲にしていきます。曲に使ったメロディーは消しゴムで消してしまい、そのカードはもう一度使っています。
戻る
3.曲の構成
- (1) 編成を決める
- 演奏会で演奏することを前提に曲を作りますので、出演者の数とか技術レベルによって編成を決めます。大勢で演奏するような場合は、たいてい一尺八寸管の三重奏曲にします。二尺三寸管を持っている人がいれば、それを入れて三重奏曲か四重奏曲にします。
- (2) 構成を決める
- 演奏会での1曲あたりの割り当て時間は10〜15分程度でしょう。これは幕間も含めての時間ですから、実質的な演奏時間は7〜12分になります。短めであれば3楽章に、長めであれば4楽章にしますが、最近は3楽章にすることが多く、独奏部分で時間を調整しています。
だいたいの形式としては3部形式が多いのですが、演奏会で初めて聴く人にとっては、旋律が再現されるため、この形式が最も適していると考えるからです。3楽章の場合、
(A+B+A’)+独奏+(C+D+C’)+独奏+(E+F+E’)
という構成を基本にしています。この前後に導入部とコーダをつけることがあります。楽章といっても、西洋音楽のようにはっきり曲を切って演奏するのではなく、独奏部を加えて自然に曲が進行していくようにしています。独奏部を加えるのは、都山流本曲からヒントを得ました。
戻る
4.楽譜を書く
- (1) 罫紙への記入
- 実際に楽譜を書いていくプロセスに特に決まったものはありません。たいていは、カードを見ながらメインの旋律を「ロツレチ」で書いていき、それにリズムや和声を追加していきます(和声をつけるときは、五線譜のほうがやりやすいのかもしれませんが、「ロツレチ」を「ドレミ」で読むことに慣れてくれば、苦にはなりません)。
問題は、旋律と旋律の間をどう繋ぐかですが、これは場当たり的で一概に言えません。この時は、尺八を吹きながら試行錯誤を繰り返すことが多いものです。
- (2) 音階とテンポ
- アマチュアの演奏を前提にしていますので、音階や調は尺八の開孔音だけで吹けるのを理想としていますが、同じ音階や調だけではどうしても単調になってしまうので、民謡音階を主体にして都節音階を部分的に取り入れたり、ロ調からレ調に転調したりしています。しかし、難しい指使いを入れてテクニックを誇るようなことはせず、できるだけ吹きにくくないように気を遣っています。
二尺三寸管のパートは、とりあえず一尺八寸管の指使いで書いておき、あとからまとめて二尺三寸管の指使いに直すようにしています。
本曲や古曲は、自分が吹いているときはいいのですが、他人が演奏しているのを聴いていると眠くなってしまうことがよくあります。それは、テンポやリズムが現代人の生活のテンポに合っていないのが原因ではないかと思います。そこで、本曲や古曲よりもテンポはやや速め(72〜120くらい)にするとともに、リズムを刻むパートを設けています。尺八の場合、音の立ち上がりに雑音が混じるので、タンギングでリズムを刻むと、パーカッション的な効果がでます。なお、年輩の方々は裏拍子が苦手なことが多いので、そのような演奏者が中心となる曲には、極力、裏拍子は避けています(けっこうこの制約条件はきついのですが……)。
- (3) 五線譜に準拠
- 都山流の楽譜は、基本的に五線譜をもとに作られていると言えますが、テンポや強弱については曖昧です。そこで、メトロノーム記号やディナーミクについては、五線譜に準拠する形で記入していきます。これは演奏者に対する指定ということだけでなく、MIDIの入力の際にも、作業が楽になります。
- (4) 演奏してチェック
- 一通り楽譜が書けたら、各パートを尺八で吹いてみて、吹きにくくないかチェックします。このときに息継ぎの記号を記入していきます。
戻る
5.清書のしかた
- (1) 清書は重要
- 以上で、曲自体はできたのですが、これをそのまま演奏者に渡しても、なかなか演奏してもらえるものではありません。鉛筆書きではゴチャゴチャして見えますし、やはり都山流の様式で楽譜を作らないと、信用してもらえないというのが実状です。作曲そのものよりも清書のほうが手間がかかりますが、これはないがしろにできません。演奏されるときの姿を思い浮かべつつ、丁寧に書いていきます。
- (2) 必要な素材
- 都山流の正式な楽譜作りの方法は知りませんが、私は、次の素材を使っています。
ケント紙(B4サイズ)
筆ペン(細)
筆ペン(極細)
サインペン(0.5mm)
ボールペン(細字)
シャープペンシル
カッター
定規(30〜40cm)
デザイン定規
消しゴム
砂消しゴム
- (3) 清書の手順
- 1) 原稿の小節数を数え、用紙の枚数を決める(通常は、最後に余白を残し、作曲年月日と簡単な解説を記入している)。
- 2) 用紙(ケント紙)を258mm×362mmにカッターで切る。
- 3) 外枠をボールペンで書く。
- 4) 各パートの音符を記入するための仮の罫線(縦線)をシャープペンシルで引く。
- 5) 小節線をボールペンで引く。
- 6) 拍子記号、メトロノーム記号、練習番号をボールペンとデザイン定規を使って記入する。
- 7) 各小節に、半分の目安となる仮の罫線(横線)をシャープペンシルで引く。
- 8) ページ番号を筆ペン(細)で記入する。
- 9) 罫線に沿って音符を筆ペン(細)で記入する。
- 10) 拍子線をサインペンで記入する(点は筆ペンで記入する)。
- 11) 甲乙、速度記号(メトロノーム記号を除く)を筆ペン(極細)で記入する。
- 12) 強弱記号をボールペンで記入する。
- 13) 表題、作曲者名を筆ペン(細)で記入する。
- 14) 原稿と対照してチェックする。
- 15) 演奏してチェックする。
- 16) 仮の罫線を消しゴムで消す。
- 17) 疲れたのでお茶を飲む。
戻る
6.MIDIの入力
- (1) ハードはお粗末
- 以上のようなかたちで曲を作っているわけですが、ホームページで曲を公開するにはMIDIデータを作らなければなりません。もともと、このようなことを考えていたわけではありませんので、私の持っているハードウェアはひじょうにお粗末です。
- パソコン
- 今となっては貴重品とも言えるDX2(66MHz)のCPU。しかもOSはWindows3.1。
- ソフトウェア
- Ballade for Windows Ver.1.1 ……バグが多いが入力は簡単。
- Cakewalk Pro Audio Ver.5.0………機能が豊富だが使いこなせていない。
- 音 源
- Roland SC-55ST
- (2) 入力方法もお粗末
- 鍵盤入力も考えたのですが、もともとできる楽器は尺八だけなので、MIDIの入力のために鍵盤楽器を習うのも遠大な計画に過ぎ、シコシコ、クリクリとマウスで入力しています。
- (3) 保存形式
- ソフトウェア固有の形式ではなく、すべて「*.mid」で保存しています。
- (4) ホームページでの公開
- FTPソフトでファイル(htmlとmid)をプロバイダーに転送します。その後、ブラウザで実際に音が鳴るかを確認して完了です。
戻る
片手間音楽製造に戻る
加羅古呂庵に戻る