アンデスで出会った人々
高橋 洋 2004年1月31日
2003年12月16日深夜、私はリマ国際空港へ降り立った。リマと言えば、ペルーの首都である。南米である。社会人として最長の3週間の休暇を取った今回の旅行では、かねてより行きたい所リストの上位に位置していたペルーに狙いを定めた。何故ペルーなのか?マチュピチュの遺跡やナスカの地上絵は誰でも良く知っているだろう。日本からは遠いし治安が心配・・・だが、機会があれば是非行ってみたい国、というイメージを持っている人も多いのではないか。しかし私にとってペルーとは、それら世界的に有名な観光地以上に、6000m級の山々が連なるアンデス山脈、そしてその大地に息づく世界こそが、強い憧れの対象だったのである。
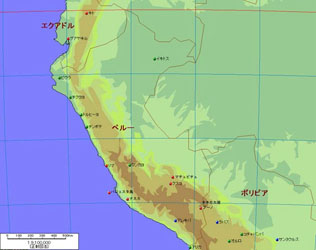 ①深夜のペルー入国
①深夜のペルー入国
東京からペルーへ行く場合、一般的にアメリカ経由となる。今回初めてコンチネンタル航空を利用したが、これはヒューストン経由。デルタならアトランタ、アメリカンならダラスと、それぞれのハブ空港で一回乗り換えただけで、リマまで行ける。12月16日の17時に東京を出発し、同日の13時半にヒューストン着。そして16時ヒューストン発でリマには23時半着。そう、意外にもその日の内に、日本の裏側のペルーに到着するのだ。飛行時間は、11時間半+6時間半=18時間。それは我慢するとして、問題はその深夜という到着時間だ。
深夜のリマ国際空港の到着ロビーには、無数の旅行業者やタクシー運転手が群がり、海外からの客を捕まえようと手薬煉引いて待っていた。これは他の発展途上国でもお馴染みの光景であり、私の旅行者然とした格好を見て、次ぎから次ぎへと魔の手が伸びてきた。いつもなら強い態度で無視して市内へのローカルバスを探すのだが、今回は到着の時刻が時刻である上治安が治安の国である。待ち構える人の余りの多さに私も一瞬たじろいでしまったが、気持ちを落ち着かせてその群集をしばらく見廻すと、私の名前が書かれた札が、群集の後ろの方で、それでもしっかりと掲げられているのが見えた。それは、今晩の宿であるオテル・サンアントニオ・アバッドからの出迎えだった。今回は私には珍しく一泊目の宿を予約し、更に空港まで迎えに来てもらっていたのだ。
 手を振りつつ人ごみを掻き分けて、その札の方へと進む。やっと握手ができた。それがペドロおじさんである(写真)。やはり、安心した。何と言ってもペルーである。「地球の歩き方」にも散々脅かすようなことが書かれている。恐らく私がこれまで訪れた国々の中で、史上最悪の治安であろう。そんな知り合いもいない国で、初めに足を踏み入れた空港において、私だけを待っている人がいるというのは、しかもそれが朴訥ながら信頼できそうな人であるというのは、何とも嬉しいことである。
手を振りつつ人ごみを掻き分けて、その札の方へと進む。やっと握手ができた。それがペドロおじさんである(写真)。やはり、安心した。何と言ってもペルーである。「地球の歩き方」にも散々脅かすようなことが書かれている。恐らく私がこれまで訪れた国々の中で、史上最悪の治安であろう。そんな知り合いもいない国で、初めに足を踏み入れた空港において、私だけを待っている人がいるというのは、しかもそれが朴訥ながら信頼できそうな人であるというのは、何とも嬉しいことである。
まだしつこく追いすがるタクシー運転手らを振り切って、「我々の」車に進む。トヨタ・カローラのライトバンだ。それに乗って空港を後にして宿へ向かう。やはり街は雰囲気が悪い。道の明かりは薄黄色で、その向こうに見える家々は、バラックのスラム街というところか。道端には深夜というのに人がたむろしている。この中で、蝿のように(失礼!)群がるタクシー運転手から一人を選び、スペイン語で値段を交渉し(この国のタクシーにはメーターなぞは無い)、全く見覚えのない街をちゃんと宿まで連れていってもらえるか。いや、できたとしても、その間の心理的負担は計り知れないだろう。
その内サンイシドロと呼ばれる地域に入り、急に街並みが良くなった。さっきまでとは明らかに住んでいる人々の「質」が違う。そうして24時半頃に、ミラフローレスというリマ一番の洗練された繁華街の片隅にあるホテルへ着いた。小規模ながらも、なかなか小じゃれたホテルだった。チェックインを済ませ、とにかく寝ることにした。飛行機に20時間近く座り続けたため相当疲れていたが、やはり14時間の時差のためよく寝られなかった。しかし、一先ず第一関門は無事突破したという、大きな安堵感があった。空港出迎えに朝食、税・サービス料込みで$39。これが事前に日本から電子メールで予約できてしまうのだから、便利な世の中になったものだ。
②アマゾンの街:イキトス
翌12月17日の主たる行動は、ペルー北東部の都市イキトスへ移動することだ。イキトスなど誰も聞いた事が無いだろうが、人口35万人のアマゾン流域の中核都市である。ペルーと聞いて、普通の人はマチュピチュの遺跡に代表されるアンデス高原を思い浮かべるだろうが、実は日本の3.4倍というその国土の50%はアマゾン河流域の熱帯雨林セルバである。アマゾンと言っても河口はブラジルの大西洋岸であり、ここペルーは源流地域に当たる。何と、河口から3700km(東京~博多間が1200km)も遡っているのだが、そのイキトスですら川幅は5kmもあり、大きな輸送船まで運行している。イキトスは木材や野菜と言ったアマゾンの物資の輸送拠点なのだ。わざわざ飛行機に乗ってまでイキトスへ向かう目的は只ひとつ。ジャングルツアーである。
12時リマ発のアエロコンチネンテ航空に乗り、13時半にイキトスへ到着した。空港を出ると、雨期のため雨がちであるが、熱帯のわりには意外と涼しい。案の定必死の形相のタクシー運転手や旅行業者が殺到してきたが、昨夜のリマと比べるとまだ明るいこともありこちらに余裕がある。一番真剣そうな目をしているお兄ちゃんに、「モトタクシーでレアル・オテル・イキトスまでいくら?」と聞くと、「ウノ・ソル」という返事が返ってきた。ペルーの通貨1ソル=約30円である。「歩き方」によれば、空港から街中までの相場は8ソルだったが、そのお兄ちゃんは1ソルだと言うのだ。安過ぎる。「ウノ・ソル?」と何度も聞き直したがそうだと言うので、その真面目そうな顔を信じて付いて行く。
 モトタクシーとは、オートバイの後ろに二人掛けの座席を付けた、タイのトゥクトゥクのような乗り物だ。モーターバイクのタクシーだからモトタクシーと言うのだろう。エンジン音が煩く座席は簡素だが、普通のタクシーの半額ぐらい。空港を出発すると、マークスというその運転手は何度も後ろを振り返って私に愛想を振り撒いてくる。その内、オテルのレコメンダシオンはオテル・アマソンだ、ジャングルツアーはシンチクイロッジがいいなどと、しきりに勧めてくる。この勧めに乗ると、彼ら客引きには何がしかのマージンが落ちるという仕組みなのだ。だからこそ、ウノ・ソルでも乗客を捕まえる方が得策ということなのだろう。NTTドコモもびっくりというビジネスモデルが、ここアマゾンには存在した。適当に相手をしつつ、20分ぐらいでアマゾン河(写真)が見えてきたと思ったら、モトタクシーはレアル・オテル・イキトスに到着した。結局彼のビジネスモデルは成功しなかったため、ウノ・ソルでは大赤字になる。渋い顔をしていたので、ドス・ソル(=60円)を渡し、そのままチェックインする。
モトタクシーとは、オートバイの後ろに二人掛けの座席を付けた、タイのトゥクトゥクのような乗り物だ。モーターバイクのタクシーだからモトタクシーと言うのだろう。エンジン音が煩く座席は簡素だが、普通のタクシーの半額ぐらい。空港を出発すると、マークスというその運転手は何度も後ろを振り返って私に愛想を振り撒いてくる。その内、オテルのレコメンダシオンはオテル・アマソンだ、ジャングルツアーはシンチクイロッジがいいなどと、しきりに勧めてくる。この勧めに乗ると、彼ら客引きには何がしかのマージンが落ちるという仕組みなのだ。だからこそ、ウノ・ソルでも乗客を捕まえる方が得策ということなのだろう。NTTドコモもびっくりというビジネスモデルが、ここアマゾンには存在した。適当に相手をしつつ、20分ぐらいでアマゾン河(写真)が見えてきたと思ったら、モトタクシーはレアル・オテル・イキトスに到着した。結局彼のビジネスモデルは成功しなかったため、ウノ・ソルでは大赤字になる。渋い顔をしていたので、ドス・ソル(=60円)を渡し、そのままチェックインする。
因みに、私はスペイン語を一度も勉強したことがないが、なんちゃってレベルであれば話すことができる。5年前に平田泰隆と2週間アルゼンチン旅行をした時に、余りにも英語が通じない現実に直面し、生きて行くために必要な範囲で覚えてしまった。だから今回の独り旅でも、何とかなるだろうと高をくくっていた。ありがたいことに、スペイン語の発音はローマ字発音であるため日本人には易しい。その上英単語に近いものが多いので、大した努力をしなくてもなんちゃってレベルにはすぐ到達できる。空港はAeropuerto:アエロプエルト、旅券はPasaporte:パサポルテ、バスターミナルはBus Terminal:ブス・テルミナル、などなど。それから、Hは発音しないからHotel:オテル、JはHの発音だからJapon:ハポン。後は、ありがとう:グラシアスに、いくら:クアント・バーレ、それにビール:セルベッサを覚えていれば、何とかなるものだ。
さて、その日は明日以降のジャングルツアーの予約をしなければならない。ジャングルツアーとは、各旅行会社が保有している熱帯雨林にあるロッジへのツアーで、全食事付きの宿泊代の他、イキトスからのボート代、熱帯雨林のトレッキング、その他イベント、そのためのガイド代など、全て込み込みで一泊二日で$80であった。より本格的な熱帯雨林を味わいたい向きには、更に奥地にあるロッジへの長期間のツアーや、テントで泊るツアーもあるという。パセオ・アマソナスという旅行代理店で予約をしたのだが、それは偶々さっきのモトタクシーの運転手が勧めた旅行会社であり、何と彼はしつこくここまで付いて来ていた。最終的に彼のビジネスモデルが成功したかは解らない。
③メルカドとマレコン・タラパカ地区
 その後イキトスの街の中を歩く。私はどこの街に行っても、必ず「市場」を訪れることにしている。市場:メルカド(Mercado)ではその街の人々の活気を感じることができ、生活を垣間見ることができる。今回のペルーでも滞在した全ての街でメルカド訪問をしたが、イキトスのメルカドでも、毛をむしり取られた鶏が何羽も吊るされ、獲ったばかりのアマゾンの魚から果物や野菜まで所狭しと並べられていた。その中で、恰幅のいいおばちゃんや小さな子供が大声で叫び、笑い、物を売り買いしていた(写真)。確かに足元は不潔で臭いもきついものがあり、女性には向かないかもしれないが、私はそういう市場を巡って人々と話をするのが大好きだ。また一角にはちょっとしたものを食べさせてくれる屋台が必ずあり、50円とか100円で荒削りだが美味しいものが食べられる。
その後イキトスの街の中を歩く。私はどこの街に行っても、必ず「市場」を訪れることにしている。市場:メルカド(Mercado)ではその街の人々の活気を感じることができ、生活を垣間見ることができる。今回のペルーでも滞在した全ての街でメルカド訪問をしたが、イキトスのメルカドでも、毛をむしり取られた鶏が何羽も吊るされ、獲ったばかりのアマゾンの魚から果物や野菜まで所狭しと並べられていた。その中で、恰幅のいいおばちゃんや小さな子供が大声で叫び、笑い、物を売り買いしていた(写真)。確かに足元は不潔で臭いもきついものがあり、女性には向かないかもしれないが、私はそういう市場を巡って人々と話をするのが大好きだ。また一角にはちょっとしたものを食べさせてくれる屋台が必ずあり、50円とか100円で荒削りだが美味しいものが食べられる。
初めてのスペイン語圏であるアルゼンチンを旅行した時にも、買いたいものが有っても無くてもメルカドには頻繁に立ち寄った。すると、どの街にも"Super Mercado"という小奇麗なスーパーがあることに気付いた。余りにもよく見かけるので、アルゼンチン版イトーヨーカドーなのかなあと思っていたら、それはただ単に「スーパーマーケット」と一般名詞を冠していたに過ぎなかったことに後で気づくことになる。ペルーにはそういう文明的なメルカドは少なかったが、イトーヨーカドーよりアメヤ横丁の方が面白いことは言うまでも無い。
 イキトスのメルカドはアマゾン河に沿って広がっているのだが、その河と市場の間、即ち河岸は、マレコン・タラパカ地区というスラム街になっている。河より高い所にある市街はスペインのコロニアル調でそれなりに整っているが、ここには木造の掘建て小屋に屋根は椰子の木の葉で作られた、見るからにボロボロの家が密集している(写真)。雨期の最盛期にはアマゾン河の水位が数メートルも上がるので、それらの家は全て「高床式」になっており、運河と化した水上をカヌーで移動できるらしい。メルカドとその地区とは何箇所かが階段で繋がっており、人がたくさん行き来している。よおく観察すると、さっきから私がおちょくってきた市場の人々は、この地区から来ている人が多いようだ。さっきから階段を下りてこの中を見学したい衝動に駆られながらも、やはり治安上の心配から思い止まっていたが、この市場のおばちゃん達の家なら大丈夫だろうと腹をくくり、愛想を振り撒きながら階段を下りてみる。
イキトスのメルカドはアマゾン河に沿って広がっているのだが、その河と市場の間、即ち河岸は、マレコン・タラパカ地区というスラム街になっている。河より高い所にある市街はスペインのコロニアル調でそれなりに整っているが、ここには木造の掘建て小屋に屋根は椰子の木の葉で作られた、見るからにボロボロの家が密集している(写真)。雨期の最盛期にはアマゾン河の水位が数メートルも上がるので、それらの家は全て「高床式」になっており、運河と化した水上をカヌーで移動できるらしい。メルカドとその地区とは何箇所かが階段で繋がっており、人がたくさん行き来している。よおく観察すると、さっきから私がおちょくってきた市場の人々は、この地区から来ている人が多いようだ。さっきから階段を下りてこの中を見学したい衝動に駆られながらも、やはり治安上の心配から思い止まっていたが、この市場のおばちゃん達の家なら大丈夫だろうと腹をくくり、愛想を振り撒きながら階段を下りてみる。
余談だが、治安が必ずしもよくない国において、「愛想を振り撒く」というのは重要である。勿論、始めからこちらの金品を狙っている根っからの悪には、そんなもの全然通用しないだろう。しかし、擦れ違う人々に対して"ブエノス・ディアス"と声をかければ、必ず向こうもにやっと笑い返し、どこから来たのかと応えてくれる。そうしておばちゃんや子供が集まってきて、写真を撮ったりする。この中で、相手に敵意や悪意が生まれる可能性は非常に低い。また、偶々その近くで悪意を持った人が狙っていたとしても、この人だかりの中では襲いにくくなる。勿論治安上の理由だけでなく旅自体が楽しくなるため、私は海外を旅行すれば必ず「いい人」になってしまう。

 で、そのマレコン・タラパカ地区だが、とっても面白かった。始めは周りを気にしながらおっかなびっくりだったが、街中を板張りの「通路」が縦横無尽に走っており、結構便利にできている(左写真)。勿論、それら全てが高床式であり、足元2mぐらい下には地面(川底)が見えている。汚水をそのまま下に垂れ流していると見えてかなりの異臭を発していたが、我慢して20分ほどゆっくり歩く。こちらから愛想を振り撒いていると、子供達が寄ってくる。デジカメを撮って見せ、文明の畏怖を感じさせる作戦にでる(右写真)。やはり「いい人」は安全なのだ。
で、そのマレコン・タラパカ地区だが、とっても面白かった。始めは周りを気にしながらおっかなびっくりだったが、街中を板張りの「通路」が縦横無尽に走っており、結構便利にできている(左写真)。勿論、それら全てが高床式であり、足元2mぐらい下には地面(川底)が見えている。汚水をそのまま下に垂れ流していると見えてかなりの異臭を発していたが、我慢して20分ほどゆっくり歩く。こちらから愛想を振り撒いていると、子供達が寄ってくる。デジカメを撮って見せ、文明の畏怖を感じさせる作戦にでる(右写真)。やはり「いい人」は安全なのだ。
④アマゾンのお手軽ジャングルツアー
12月18日午前10時に、旅行会社までバックパックを背負って出向く。停まっていたツアーバスに乗り込むと既に5,6人の先客がいたが、一部の人々がスペイン語でべらべら会話をしていた。何事も初めが肝心だが、これでは愛想を振り撒きようもない。やばいなあと思っていると、ガイドとおぼしき陽気なセニョールが乗ってきた。が、この人もスペイン語をべらべら喋っている。や、や、やばい。旅行会社では「英語のガイド」と言っていたのに!。去年の中国・大理のツアーの二の舞かと不安になってきたが、その内別のヨーロッパ人とおぼしき男性が、「英語でも喋ってくれ」と言ったところで、ガイドはスペイン語と英語の両方で話をしてくれるようになった。
 結局総勢13名が、スペイン人の老夫婦x2+若夫婦、メキシコ人の家族4人、そしてスイス人2人と日本人は私1人ということが解ったのは、アマゾン河を30分ほどボートで下り、支流のシンチクイ川の側にある立派なロッジに着いてランチを食べ終わった頃だった。たまたまそのツアーで一緒になったというスイス人2人は、私よりは数倍ましだろうがスペイン語がそれほど上手くないため、必然的にこの3人は仲良くなり、ガイドとしても英語で話す時はこの3人向けということで、3人が近くに座ることが多くなった。先進国の小国特有の寛容さも備えているこの2人とは、このジャングルツアーを通して非常に仲良くなることができた(写真)。
結局総勢13名が、スペイン人の老夫婦x2+若夫婦、メキシコ人の家族4人、そしてスイス人2人と日本人は私1人ということが解ったのは、アマゾン河を30分ほどボートで下り、支流のシンチクイ川の側にある立派なロッジに着いてランチを食べ終わった頃だった。たまたまそのツアーで一緒になったというスイス人2人は、私よりは数倍ましだろうがスペイン語がそれほど上手くないため、必然的にこの3人は仲良くなり、ガイドとしても英語で話す時はこの3人向けということで、3人が近くに座ることが多くなった。先進国の小国特有の寛容さも備えているこの2人とは、このジャングルツアーを通して非常に仲良くなることができた(写真)。
 さて、まずはカヌーで近くに住む部族の村を訪れる。いかにも熱帯雨林の中にありそうな木で出来た高床式の家々に、半分裸族という人々がいた(写真)。まさにウルルン滞在記に出てきそうな環境の中で、彼らの唄を聴き、踊りを見る。ツアーの初っ端から、これは強烈に印象に残った。彼らは吹き矢を実演し、一通りの「儀式」をこなし、最後にお土産の販売が始まった。これは購入する義務はないのだが、子供達がお手製の首飾りや置物を持ってすがって来ると、さすがに冷たくはしづらい。仕方なく首飾りを5ソル(=150円)で買った。イキトスの街中での相場より数倍高い。
さて、まずはカヌーで近くに住む部族の村を訪れる。いかにも熱帯雨林の中にありそうな木で出来た高床式の家々に、半分裸族という人々がいた(写真)。まさにウルルン滞在記に出てきそうな環境の中で、彼らの唄を聴き、踊りを見る。ツアーの初っ端から、これは強烈に印象に残った。彼らは吹き矢を実演し、一通りの「儀式」をこなし、最後にお土産の販売が始まった。これは購入する義務はないのだが、子供達がお手製の首飾りや置物を持ってすがって来ると、さすがに冷たくはしづらい。仕方なく首飾りを5ソル(=150円)で買った。イキトスの街中での相場より数倍高い。
日本人なら誰でも驚き、喜ぶであろうその体験を通して、やはり複雑な感情を持たざるを得ない。彼らは毎日このような「文明人」からの訪問を受け、お決まりの儀式を行いお土産を売ることによって、生計を立てているのであろう。よく聞いてみると、元々別の地域に住んでいたものを、旅行会社からその土地を与えられて移住したとのこと。もしかしたら、その裸族のような格好も昼間だけのもので、夜になるとTシャツに着替えてしまうのかもしれない。彼らの本当の気持ちを考えると、自分もその「悪行」に加担していることについて、苦い気持ちになってしまった。
その後、ロッジの周辺の熱帯雨林をトレッキングする。確かに熱帯雨林の中を歩き、巨大な木や草花を見て回るのは貴重な体験だったが、そこは毎日こうして旅行客が通って踏み固められた道である。特別きれいな蝶が乱舞するわけでもなく、珍しい野生動物に出会うわけでもない。たまにガイドが、この木からは水が飲めるとか、この草には毒があるとか説明してくれるが、まあその程度であった。1時間ほどかけて熱帯雨林をぐるっと周り、最後にサンタマリアという小さな村に出た。そこでは普通のシャツやズボンを履いた人々が普通の家々に暮らしていたが、実は我々が泊っているシンチクイロッジは、その村から徒歩5分であることに、その直後に気付くことになる。
ロッジは椰子の葉や木でできている高床式の熱帯雨林そのものの作りであり、電気は無いものの夜にはランプが各部屋に配られ、逆に秘境ムードを盛り上げてくれる。質素ながらも非常に快適で、各部屋にはちゃんとしたベッドからシャワー・トイレまで付いている。食事もそれなりに充実しており、お金さえ払えば冷たいビールでもコーラでも飲むことができる。お蔭で気の合った仲間と一泊二日を楽しく過ごし、少しでもアマゾン気分を味わうことができた。それはまさに私のような観光客向けの旅行サービスであり、喜ばなければならない。一方で、やはり飛行機が就航している街からの一泊二日のジャングルツアーとはこんなものかと言い捨ててしまうのは、身勝手だろうか。
⑤舐めたらあかん・リマの治安
12月19日の21時半にリマ国際空港へ戻る。今夜は宿の予約は無く、勿論迎えも来ていない。既に外は真っ暗だったが、これまでの数日間でペルーのリズムは掴みつつあるとの思いがあった。やや緊張しながら空港を出て、案の定殺到してきたタクシーの運ちゃん達に対して、「セントロ(旧市街)までいくら?」と聞く。始めは「10ドル」とかふざけたことを言ってきたが、その内20ソルになり、最終的には相場である15ソル(=450円)に落ち着いた。やはりペルーと言えどもこちらが毅然とした態度を示せば何とかなるものだ。
リマは人口774万人を擁する南米有数の大都市だが、長らく中心地であったセントロの治安は悪化する一方で、オフィス街やホテルなどは前記のミラフローレスへ移っているようだ。旅行者はミラフローレスに宿を取り、歴史的建造物が多いセントロには昼間に訪れることが多いとのことだが、私は翌朝なるべく早くナスカ往きのバスに乗りたかったため、バスターミナルがあるセントロに宿泊することにしたのだ。夜遅いとは言えど、タクシーで乗りつけてホテルに泊るだけなら大丈夫だろうと思ったのである。
22時頃に、セントロの中心地サンマルティン広場に面したオスタル・サンマルティンに到着する。メキシコシティーでも思ったことだが、どうも南米では街灯の色が良くない。日本でお馴染みの白色灯ではなく橙色のため、街自体が怪しく見えてしまう。サンマルティン広場には夜遅いというのに多くのペルー人がたむろしており、明らかに雰囲気は悪い。オスタルの入り口を入ると、二階へ上がる階段の途中に更にドアがあり鍵がかかっていた。焦りつつドンドンと叩くと上から日系人と思われる宿の人の顔が覗き、開けてくれた。ほっとして二階へ上がり、チェックインを済ます。一泊朝食付きで$30。NHKの日本語放送まで見られる。
その晩夕食は食べていなかったため、ちょっと買い物に出たかった。宿の人に治安の状況を聞くと、余りこの時間からの外出は勧めないと言われた上で、
・このホテル前の道の左側へは2ブロック以上行ってはいけない
・買い物をするとすれば、北側の通りを数ブロック程度
・腕時計は盗られるのではずして行くように
とのこと。リュックも背負わず小銭だけをポケットに忍ばせて、ペルー人になった積もりで外に出る。やはり怪しい雰囲気だ。所々に警官が立っているので良いが、誤った方向に行くと相当危なそうである。勧めてくれた北側の道は繁華街と見えて、普通の格好をした庶民が大勢歩いている。そこで飲み物と食べ物を買ってすぐに宿へ戻る。
翌朝、7時に宿を出て徒歩10分の距離にあるバスターミナルに向かう。しかしここでも、宿の人から歩いて行くのはやめた方が良いと言われ、素直に勧めに従ってタクシーに乗る。運転手は「ここはノー・セキュリティ。ここはセキュリテ」」などと得意気に説明していたが、すぐにバスターミナルに到着した。警官が複数立っていたものの、その辺りも相当殺伐とした雰囲気だ。ペルーではバスが公共交通機関の主流で複数のバス会社が全国に路線網を持っているが、その中でも大規模で信頼の高いオルメーニョ社の窓口で、8時半発ナスカ往きのバスに乗りたいと告げる。すると、6時間半の乗車時間にも関わらずわずか30ソル(=900円)だと言う。「歩き方」によれば60~80ソルとのことだったので、これは相当安い。そのバスはエコノミークラスであり、その上に普通の外国人旅行者が利用するビジネスクラスとロイヤルクラスがあるからだった。
車の快適さは我慢すれば良いのだが、昨夜から治安について相当脅かされている自分としては、このバスターミナルから一刻も早く立ち去りたかった。そこまで付いて来ていたタクシーの運転手に相談すると、「サンイシドロにオルメーニョ社のロイヤルクラスやビジネスクラスのブス・テルミナルがあるので、そっちへ行けば良い」という。それは「歩き方」にも書いてあったのだが、そちらはロイヤルクラスのみという書き方であったためわざわざセントロの方へ来たのだ。が、治安が悪化する一方のセントロからは、最早現地人が乗るバスしか出発しないような雰囲気であった。
意を決してサンイシドロ地区へ移動する。こちらのバスターミナルはセントロのそれとは全く雰囲気が違う。日本にもありそうな快適な窓口であり、英語もある程度通じ、白人旅行者も多数いた。やはりこちらへ来てよかったと安心して窓口で聞いてみると、午前中に出発するナスカ往きは満席だと言う。これは困った。いろいろ迷ったが、結局セントロへ戻り、先程のエコノミークラスのチケットを購入する。待合室には外国人旅行者とおぼしき人は殆ど見当たらず、相当心細い思いをしたが、30分遅れでバスはナスカへ向けて発車した。
相当古いながらも一応観光バスの体をしたそのバスは、一人の日本人と多数のペルー人を乗せて、太平洋を右手に見つつパンアメリカン・ハイウェイを南下する。そこに展開される情景はモロッコやアメリカ西部と同様の土の砂漠であり、改めてこの辺りが砂漠気候であることを認識させられる。途中1時間に一度ぐらいの割合で停車し、乗客が乗り降りする。自分のバックパックは車内へ持ち込み常に気をつけるが、ひと先ず周りの目が光ってはいないようだ。結局食事休憩も挟み予定の1.5倍近くの時間がかかって、何とか無事にナスカに着いたのは18時前だった。
⑥消えゆくナスカの地上絵
必死の思いで辿り着いたナスカは、発展途上国の観光地にありがちな、開放感に溢れるこぢんまりとした街だった。バスを降りて、地上絵ツアーの客引きが群がる中、まだ明るかったので歩いて宿探しに向かう。観光のためだけに存在しているような砂漠の街であり、街中にはレストランや旅行会社も目立つが、オフシーズンだからか比較的のんびりしたムードが漂い、その垢抜けない雰囲気が逆に微笑ましかった。片言の日本語を話す人も寄って来るが、それほどしつこくはない。大都市リマのような緊張感もなく、ようやくオアシスで一息着けそうだ。
バス停から徒歩5分、中心地のアルマス広場へも5分という好位置にある、オロ・ビエホというオスタルにチェックインする。因みにHostalとは、Hotelに対して小規模の家族経営的な、日本で言えばペンションのような宿泊施設である。豪華ではないが、バス・トイレなど一通りの設備は整っており、2つ星のオテルであれば3つ星のオスタルの方が良い事も多く、今回の旅行では随分とお世話になった。ここは平屋建てのこぢんまりとしたオスタルだが、まだ新しく清潔で、白に統一された内装もなかなかセンスが良く、女性に好まれそうなプチホテルという感じか。朝食付きで$20。その後遊覧飛行で有名なアエロ・コンドル社の地上絵ツアーの予約に行く。パイロットを含めて4人乗りのセスナ機で30分間飛行して$35。その日はとにかく心身ともに疲れていたので、そのまま宿に戻り眠りに着く。
翌日の12月21日、午前10時に迎えのバスがオスタルに来てくれ、近くの空港まで連れて行ってくれる。セスナ機しか着陸できない小規模の空港で、比較的閑散としていた。すぐにセスナ機に乗り込んだのは、私と40代ぐらいのドイツ人夫妻。セスナ機に乗るのは初めてだったが、陽気なパイロットからその場で地図を渡され、どの地上絵をどの順番で回るかを英語で解りやすく説明してもらった。エンジンがかかり気持ちが高ぶる中、シートベルトにヘッドフォンを着用して早速離陸する。
 2、3分北上した後、いよいよ最初の地上絵である「鯨」の上を遊覧する。パイロットはご丁寧にも「あれが鯨」と指差してくれたが・・・、すぐには解らない。思ったより小さく、かつはっきりと見えないのだ。その後「宇宙飛行士」、「猿」と続き、かなり慣れてきたがやはり識別しにくい。私はてっきり、飛行機に乗れば誰に言われなくても目の前に大きな地上絵が広がるものと思い込んでいたが、実際にはそうではなかった。その後、有名な「ハチドリ」(写真)、「木」、「オウム」など10以上の地上絵を見て回り、結局40分間程遊覧して元の空港へ戻る。確かに荒野にあのような地上絵が書かれているのは神秘そのものだが、軽く酔ったこともあり、「大感動」というわけにはいかなかった。宿に戻ってデジカメから映像をPCに落として確認してみたが、実際に見た自分でさえ何処に何が写っているのかすぐには解りづらかった。
2、3分北上した後、いよいよ最初の地上絵である「鯨」の上を遊覧する。パイロットはご丁寧にも「あれが鯨」と指差してくれたが・・・、すぐには解らない。思ったより小さく、かつはっきりと見えないのだ。その後「宇宙飛行士」、「猿」と続き、かなり慣れてきたがやはり識別しにくい。私はてっきり、飛行機に乗れば誰に言われなくても目の前に大きな地上絵が広がるものと思い込んでいたが、実際にはそうではなかった。その後、有名な「ハチドリ」(写真)、「木」、「オウム」など10以上の地上絵を見て回り、結局40分間程遊覧して元の空港へ戻る。確かに荒野にあのような地上絵が書かれているのは神秘そのものだが、軽く酔ったこともあり、「大感動」というわけにはいかなかった。宿に戻ってデジカメから映像をPCに落として確認してみたが、実際に見た自分でさえ何処に何が写っているのかすぐには解りづらかった。
ナスカの地上絵は、インカ時代の前、紀元後5世紀頃に書かれたという。線に見えるものは、黒い地表の小石を取り除いた白くて浅い溝なのだが、雨が殆ど降らない地域であるため今でもそのまま残っているとのこと。英語では"Nazca Lines"いうのだが、その「線」は毎年少しづつ薄くなっており、保存の必要性が強く叫ばれているようだ。何のためにこのようなものが描かれたかは未だ解明されていないのだが、その前に線自体が消えてしまってはどうしようもない。確かに世界の七不思議の一つと言える代物だろうが、私には呆気なく終わってしまった。
⑦クリスマスはバスも運休
今回3週間という久々の大旅行になった。1週間少々の旅だと、この辺りでそろそろ帰国の途に着かなければならない。その点3週間あると違う。3週間の旅が1週間の旅と決定的に違うのは、「旅そのものが日常になる」ということだ。今日も旅、明日も旅、明後日も旅。ナスカの次はアレキパ、アレキパからアンデスを越えてラパス、次は憧れのティティカカ湖と、今日も当たり前のように新たな街に移動し、新たな宿を決めて新たな空気に触れる。そしてまた次の街へ移動する。このリズムが体に染み付き、旅そのものが当たり前の日常になる。1週間の旅では、前の街で入国したところでも、次の街では最早帰国しなければならない。旅の終わりが始めから見えているのだ。今回は、旅をしているんだなあと、心から感じることができた。
ナスカの地上絵を見た12月21日の夜22時頃、夜行バスでナスカを後にする。今度はちゃんとビジネスクラス。これで飛行機のエコノミークラス程度の椅子か。トイレも社内に付いている。9時間の行程で70ソル(=2100円)。乗客も半分以上は外国人旅行客で、昼間に遊覧飛行で一緒だったドイツ人夫妻も偶然一緒だった。次の目的地アレキパは、ペルー南西部にある人口90万人のペルー第二の都市。海抜2000m以上の高原にあるので一年中気候が温暖であり、金持ちがたくさん住んでいる美しい街だ。旅行客にとっての目当ては、この近くにあるキャノン・デ・コルカル(コルカル渓谷)へ行くこと。アメリカのグランドキャニオンにも負けない深い渓谷で、その上をコンドルが悠然と飛んでいる姿が見られるという。国立公園評論家である私の目当ても、勿論ここへの一泊二日のツアーであった。
12月22日の朝7時頃にアレキパのバスターミナルに到着。23、24日とツアーに参加する積もりなので、24日夜のアレキパ発ラパス往きのチケットを予約しておく。と・こ・ろ・が・・・その便はその日は走らないという!。25日はクリスマスで、ペルー国民にとって一番大切な祝日。従って、24日のラパス往き夜行便は勿論、25日のクスコやリマ往きの昼行便も全て運休するとのこと。他のバス会社に聞いてみても、やはり25日には全て運休と言われた。コルカル渓谷を諦めて先へ進むか、ラパス・ボリビアを諦めてここを26日に出るか…、30分ぐらいバス会社のカウンターをうろうろして悩みに悩んだが、訪問国をもうひとつ増やすことを優先することにした。
⑧ユーラ温泉
 ということで、アレキパでは一泊二日になってしまったが、ならばと、もうひとつどうしても行きたかった近郊の「ユーラ」へは確実に行くことにする。アレキパの周りには標高6000m以上の山々が聳えており、富士市もびっくりという絶景(写真)なのだが、その山麓に何と温泉が湧いているのである。ペルーは日本に負けないぐらいの火山国であるため、ここユーラに限らず温泉が湧いているところが多い。オスタルにチェックイン後ランチを食べて、コレクティーボ(ローカルバス)に乗ってユーラ温泉へ向かう。そのコレクティーボは、ご丁寧にも「みなみかしわようちえん」の表示を残した、日本から輸入された中古車だった。
ということで、アレキパでは一泊二日になってしまったが、ならばと、もうひとつどうしても行きたかった近郊の「ユーラ」へは確実に行くことにする。アレキパの周りには標高6000m以上の山々が聳えており、富士市もびっくりという絶景(写真)なのだが、その山麓に何と温泉が湧いているのである。ペルーは日本に負けないぐらいの火山国であるため、ここユーラに限らず温泉が湧いているところが多い。オスタルにチェックイン後ランチを食べて、コレクティーボ(ローカルバス)に乗ってユーラ温泉へ向かう。そのコレクティーボは、ご丁寧にも「みなみかしわようちえん」の表示を残した、日本から輸入された中古車だった。
 1時間程経ち、幼稚園児用の小さな椅子にお尻が痛くなって来たところで、こちらが何も言わないのに車掌が降りろという。外国人は私だけで他の乗客は誰も降りないのだが、言う通りに降りてみるとそこは小さな渓谷沿いに緑のオアシスが続くのどかな景色が広がっており、目の前には「オテル・ユーラ」があった。ユーラ温泉についての詳しい情報は「歩き方」に書いてなかったのだが、おっかなびっくりその閑散としたホテルのフロントに行ってみる。何とか温泉に入りたい旨を伝えると、フロントの人の良さそうなオヤジが満面の笑みで温泉のことをひと頻り説明してくれたようだが、スペイン語なのでよく解らない。ともかく5ソル(=150円)の入浴代を払って温泉へ案内してもらう。ちょっとした倉庫のような建物の中に入ると、確かにあるあるお風呂が。本格的な硫黄の臭いが充満している中に、家庭用のお風呂を3つ繋げたような大きさの浴槽が4つある。浴槽といっても深さは1mぐらいあって、プールに入る前の消毒槽と言うイメージか(写真)。家族連れの先客が7,8名いたが、みんな水着で入っている。
1時間程経ち、幼稚園児用の小さな椅子にお尻が痛くなって来たところで、こちらが何も言わないのに車掌が降りろという。外国人は私だけで他の乗客は誰も降りないのだが、言う通りに降りてみるとそこは小さな渓谷沿いに緑のオアシスが続くのどかな景色が広がっており、目の前には「オテル・ユーラ」があった。ユーラ温泉についての詳しい情報は「歩き方」に書いてなかったのだが、おっかなびっくりその閑散としたホテルのフロントに行ってみる。何とか温泉に入りたい旨を伝えると、フロントの人の良さそうなオヤジが満面の笑みで温泉のことをひと頻り説明してくれたようだが、スペイン語なのでよく解らない。ともかく5ソル(=150円)の入浴代を払って温泉へ案内してもらう。ちょっとした倉庫のような建物の中に入ると、確かにあるあるお風呂が。本格的な硫黄の臭いが充満している中に、家庭用のお風呂を3つ繋げたような大きさの浴槽が4つある。浴槽といっても深さは1mぐらいあって、プールに入る前の消毒槽と言うイメージか(写真)。家族連れの先客が7,8名いたが、みんな水着で入っている。
 さて、期待に胸を膨らませて温泉に入ってみると、ぬるい!。日本ではこれは温泉とは言わない。もしかしたら、ペルー人用に高温の温泉を水で冷ましているのかもしれないが、外気が20度ぐらいのため始めは寒く感じた。それでも首まで浸かっていると、じわじわと温まってくる。浴槽ごとに泉質も異なるようで、やや白濁した温泉もあった。先客は全てペルー人だったが、面白いことに湯の中で会話が弾むのは万国共通のようである。殆ど通じない中で、延々と1時間ぐらい温泉に浸かりながらスペイン語会話をしてしまった(写真)。大胆にも要約してみると、
さて、期待に胸を膨らませて温泉に入ってみると、ぬるい!。日本ではこれは温泉とは言わない。もしかしたら、ペルー人用に高温の温泉を水で冷ましているのかもしれないが、外気が20度ぐらいのため始めは寒く感じた。それでも首まで浸かっていると、じわじわと温まってくる。浴槽ごとに泉質も異なるようで、やや白濁した温泉もあった。先客は全てペルー人だったが、面白いことに湯の中で会話が弾むのは万国共通のようである。殆ど通じない中で、延々と1時間ぐらい温泉に浸かりながらスペイン語会話をしてしまった(写真)。大胆にも要約してみると、
「あんた一人で来ているのかい?」
「はい、そうです。東京から来ました。」
「日本には奥さんはいないの?」
「いえ、独身ですので。」
「あら、そんならペルーで見つければいいがね。」
多分こんな感じだったと思う。翌日もまだ体に硫黄の臭いが残り、肌もすべすべだったので、効用は確かなようだ。ややハードだったこれまでの旅も、気候が良くて爽やかなアレキパの街とのどかなユーラ温泉のお陰で気分的に随分と楽になり、今度こそ旅のリズムが掴めてきたような気がする。
⑨ボリビア入国
さて、予定より一日早い23日の夜行便で一路ラパスへ向かう。ラパスと言えば、ボリビアの首都である。ボリビア・・・皆さんはどういうイメージを持っているだろうか?。アンデスの高地にある内陸国。南米の中でも特に貧しい、などだろうが、いずれにしろ殆ど知られていないことだろう。因みに、ラパスは世界で最も高い所にある首都らしい。標高3650m。その高さ故に、訪れる外国人は高山病になるという。でも、そんな街だからこそ、是非とも訪れてみたかったのだ。
アレキパからのバスは、ビジネスクラスの更に上のロイヤルクラスにした。飛行機のビジネスクラスのような足置きがある贅沢な椅子で、朝食付き。ラパスまで12時間のチケットはちと高くて$45。アンデス山脈越えをしたはずだが、金にものを言わせたお陰か比較的よく眠れ、24日の朝に目を覚ましたら、ペルーとボリビアの国境の町デサグアデーロだった。
 陸路で国境を越えるというのは、特に日本人にとっては国境を実感できる瞬間であり、楽しいものだ。バスを下りてペルー側の出国手続きを済ます。その後どうしたらいいのか迷っていると、何時の間にか私の周りには同じバスの乗客が二人しかいなくなっていた。ヨーロッパ系のカップルのようだったが、彼らもよく解っておらず、バスに戻ってみてももう他には誰もいない。再度「歩き方」を読み直すと「歩いて国境を越える」と書いてあるので、そのカップルも誘ってそのまま前に進む。すると確かに頭の上には、"Thanks for your visit"というペルー側の看板と、その向こうに"Welcome to Bolivia"というボリビア側の看板があった(写真)。
陸路で国境を越えるというのは、特に日本人にとっては国境を実感できる瞬間であり、楽しいものだ。バスを下りてペルー側の出国手続きを済ます。その後どうしたらいいのか迷っていると、何時の間にか私の周りには同じバスの乗客が二人しかいなくなっていた。ヨーロッパ系のカップルのようだったが、彼らもよく解っておらず、バスに戻ってみてももう他には誰もいない。再度「歩き方」を読み直すと「歩いて国境を越える」と書いてあるので、そのカップルも誘ってそのまま前に進む。すると確かに頭の上には、"Thanks for your visit"というペルー側の看板と、その向こうに"Welcome to Bolivia"というボリビア側の看板があった(写真)。
3人で意を強くして進むと、すぐにボリビア側の入国管理事務所が見つかり、そこには他の乗客もいた。これで一安心。ボリビアの入国も無事済ませ、さっきまで乗っていたバスが来るのを待つ。その間そのカップルと話が弾む。二人ともイタリアのパスポートを持っていたが、奥さんの英語にはイタリア訛りが全くなく、かと言ってこてこてのクイーンズ・イングリッシュでもなかった。聞いてみると、旦那はイタリア生まれのイタリア人で、奥さんは南アフリカ生まれでイギリスに7年も暮らしているという。二人はロンドンで出会い、今もロンドンで暮らしている。この二人とは、危うく迷子になりそうになった戦友だからか、やたらと気が合う。ラパスでの宿も同じ所を考えていたことが解り、ラパスのバスターミナルから一緒に宿へ行こうと話をする。
⑩海抜3650mの首都:ラパス
お昼前にラパスに到着した。空気が薄い!!。今回の目玉であるアンデス高原の最初の都市に降り立ち、身をもってその標高を実感する。夜行バスの疲れのせいもあったかもしれないが、体全体がだるく、軽い頭痛がする。これが「高山病」か?。重症の時には頭が割れる様に痛くなり、とにかく高度を下げるしか処置方法がないという。そこまではひどくないものの、明らかに調子がおかしい。その上ラパスは坂が多いので少し歩くとすぐに息が切れる。そんな坂を駆け回っている子供達が憎たらしい。こんなところでマラソンでもやろうものなら、高橋尚子でも勝てないだろう。
 街の中は「混沌」の世界である。クリスマスイブのため特別だったようだが、人の多さにはとにかく閉口した。道という道に露店が溢れ、朝の山手線もびっくりという具合の混雑振りである。ボロボロの市バスはどれも満員で、車掌が大声で行き先を連呼しながら走っている。侵略者であるスペイン人は、アンデス下ろしの風を避けるべくすり鉢状の盆地に街を造ったため、ラパスでは鉢の底に高層ビルが並び、高級住宅街が位置している。そこから放射状かつ無秩序に坂道が延びており、上に行けば行くほど赤レンガ:アドベで造られた廃墟同然の家並みが広がっている。その光景は遠くから見ると美しく、近くから見ると異様である(写真)。
街の中は「混沌」の世界である。クリスマスイブのため特別だったようだが、人の多さにはとにかく閉口した。道という道に露店が溢れ、朝の山手線もびっくりという具合の混雑振りである。ボロボロの市バスはどれも満員で、車掌が大声で行き先を連呼しながら走っている。侵略者であるスペイン人は、アンデス下ろしの風を避けるべくすり鉢状の盆地に街を造ったため、ラパスでは鉢の底に高層ビルが並び、高級住宅街が位置している。そこから放射状かつ無秩序に坂道が延びており、上に行けば行くほど赤レンガ:アドベで造られた廃墟同然の家並みが広がっている。その光景は遠くから見ると美しく、近くから見ると異様である(写真)。
 そんな世界に暮らしている人々は、「民族的」である。ボリビアは先住民族・インディヘナが、人口の55%と南米一の多さを誇る。日に焼けて皺だらけの顔つきをし、三つ編みをして民族衣装を着ているいかにもと言うおばちゃんがペルー以上に多かった。いやがおうにも、ボリビアまでやって来たという実感が強まる。一方、ペルーほど観光化・商業化されていないからか、シャイな人が多く、写真を取らせてくれと頼んでも殆ど断られてしまった。向こうからこちらに話し掛けてくることはまずない。
そんな世界に暮らしている人々は、「民族的」である。ボリビアは先住民族・インディヘナが、人口の55%と南米一の多さを誇る。日に焼けて皺だらけの顔つきをし、三つ編みをして民族衣装を着ているいかにもと言うおばちゃんがペルー以上に多かった。いやがおうにも、ボリビアまでやって来たという実感が強まる。一方、ペルーほど観光化・商業化されていないからか、シャイな人が多く、写真を取らせてくれと頼んでも殆ど断られてしまった。向こうからこちらに話し掛けてくることはまずない。
それでもせっかくのクリスマスイブなので、先程のイタリア人夫妻と夕食に出かける。宿の近くのボリビア料理店に行き、ぶどうの蒸留酒をスプライトで割った名物カクテル:チュフライで乾杯し、リャマの焼肉を食べる(写真)。クリスマス・ディナーだけあり、一人60ボリビア-ノ(=900円)と結構な値段だ。お互いの仕事や今回の旅行の話など、2時間ぐらい盛り上がる。その後一緒に教会に行き、クリスマスのミサを体験する。スペイン語なのでさっぱり解らなかったが、徳のありそうな神父さんが厳かな雰囲気の中で有り難いお話をしていたのだろう。敬虔なクリスチャンのクリスマスの過ごし方を垣間見ることはできた。
後編へ続く
Copyright (c)2004 K.Horiuchi-H.Takahashi Allright reserved
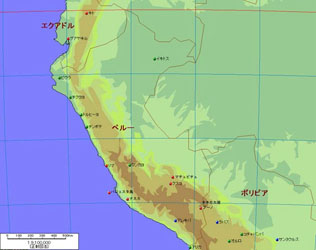 ①深夜のペルー入国
①深夜のペルー入国 手を振りつつ人ごみを掻き分けて、その札の方へと進む。やっと握手ができた。それがペドロおじさんである(写真)。やはり、安心した。何と言ってもペルーである。「地球の歩き方」にも散々脅かすようなことが書かれている。恐らく私がこれまで訪れた国々の中で、史上最悪の治安であろう。そんな知り合いもいない国で、初めに足を踏み入れた空港において、私だけを待っている人がいるというのは、しかもそれが朴訥ながら信頼できそうな人であるというのは、何とも嬉しいことである。
手を振りつつ人ごみを掻き分けて、その札の方へと進む。やっと握手ができた。それがペドロおじさんである(写真)。やはり、安心した。何と言ってもペルーである。「地球の歩き方」にも散々脅かすようなことが書かれている。恐らく私がこれまで訪れた国々の中で、史上最悪の治安であろう。そんな知り合いもいない国で、初めに足を踏み入れた空港において、私だけを待っている人がいるというのは、しかもそれが朴訥ながら信頼できそうな人であるというのは、何とも嬉しいことである。 モトタクシーとは、オートバイの後ろに二人掛けの座席を付けた、タイのトゥクトゥクのような乗り物だ。モーターバイクのタクシーだからモトタクシーと言うのだろう。エンジン音が煩く座席は簡素だが、普通のタクシーの半額ぐらい。空港を出発すると、マークスというその運転手は何度も後ろを振り返って私に愛想を振り撒いてくる。その内、オテルのレコメンダシオンはオテル・アマソンだ、ジャングルツアーはシンチクイロッジがいいなどと、しきりに勧めてくる。この勧めに乗ると、彼ら客引きには何がしかのマージンが落ちるという仕組みなのだ。だからこそ、ウノ・ソルでも乗客を捕まえる方が得策ということなのだろう。NTTドコモもびっくりというビジネスモデルが、ここアマゾンには存在した。適当に相手をしつつ、20分ぐらいでアマゾン河(写真)が見えてきたと思ったら、モトタクシーはレアル・オテル・イキトスに到着した。結局彼のビジネスモデルは成功しなかったため、ウノ・ソルでは大赤字になる。渋い顔をしていたので、ドス・ソル(=60円)を渡し、そのままチェックインする。
モトタクシーとは、オートバイの後ろに二人掛けの座席を付けた、タイのトゥクトゥクのような乗り物だ。モーターバイクのタクシーだからモトタクシーと言うのだろう。エンジン音が煩く座席は簡素だが、普通のタクシーの半額ぐらい。空港を出発すると、マークスというその運転手は何度も後ろを振り返って私に愛想を振り撒いてくる。その内、オテルのレコメンダシオンはオテル・アマソンだ、ジャングルツアーはシンチクイロッジがいいなどと、しきりに勧めてくる。この勧めに乗ると、彼ら客引きには何がしかのマージンが落ちるという仕組みなのだ。だからこそ、ウノ・ソルでも乗客を捕まえる方が得策ということなのだろう。NTTドコモもびっくりというビジネスモデルが、ここアマゾンには存在した。適当に相手をしつつ、20分ぐらいでアマゾン河(写真)が見えてきたと思ったら、モトタクシーはレアル・オテル・イキトスに到着した。結局彼のビジネスモデルは成功しなかったため、ウノ・ソルでは大赤字になる。渋い顔をしていたので、ドス・ソル(=60円)を渡し、そのままチェックインする。 その後イキトスの街の中を歩く。私はどこの街に行っても、必ず「市場」を訪れることにしている。市場:メルカド(Mercado)ではその街の人々の活気を感じることができ、生活を垣間見ることができる。今回のペルーでも滞在した全ての街でメルカド訪問をしたが、イキトスのメルカドでも、毛をむしり取られた鶏が何羽も吊るされ、獲ったばかりのアマゾンの魚から果物や野菜まで所狭しと並べられていた。その中で、恰幅のいいおばちゃんや小さな子供が大声で叫び、笑い、物を売り買いしていた(写真)。確かに足元は不潔で臭いもきついものがあり、女性には向かないかもしれないが、私はそういう市場を巡って人々と話をするのが大好きだ。また一角にはちょっとしたものを食べさせてくれる屋台が必ずあり、50円とか100円で荒削りだが美味しいものが食べられる。
その後イキトスの街の中を歩く。私はどこの街に行っても、必ず「市場」を訪れることにしている。市場:メルカド(Mercado)ではその街の人々の活気を感じることができ、生活を垣間見ることができる。今回のペルーでも滞在した全ての街でメルカド訪問をしたが、イキトスのメルカドでも、毛をむしり取られた鶏が何羽も吊るされ、獲ったばかりのアマゾンの魚から果物や野菜まで所狭しと並べられていた。その中で、恰幅のいいおばちゃんや小さな子供が大声で叫び、笑い、物を売り買いしていた(写真)。確かに足元は不潔で臭いもきついものがあり、女性には向かないかもしれないが、私はそういう市場を巡って人々と話をするのが大好きだ。また一角にはちょっとしたものを食べさせてくれる屋台が必ずあり、50円とか100円で荒削りだが美味しいものが食べられる。 イキトスのメルカドはアマゾン河に沿って広がっているのだが、その河と市場の間、即ち河岸は、マレコン・タラパカ地区というスラム街になっている。河より高い所にある市街はスペインのコロニアル調でそれなりに整っているが、ここには木造の掘建て小屋に屋根は椰子の木の葉で作られた、見るからにボロボロの家が密集している(写真)。雨期の最盛期にはアマゾン河の水位が数メートルも上がるので、それらの家は全て「高床式」になっており、運河と化した水上をカヌーで移動できるらしい。メルカドとその地区とは何箇所かが階段で繋がっており、人がたくさん行き来している。よおく観察すると、さっきから私がおちょくってきた市場の人々は、この地区から来ている人が多いようだ。さっきから階段を下りてこの中を見学したい衝動に駆られながらも、やはり治安上の心配から思い止まっていたが、この市場のおばちゃん達の家なら大丈夫だろうと腹をくくり、愛想を振り撒きながら階段を下りてみる。
イキトスのメルカドはアマゾン河に沿って広がっているのだが、その河と市場の間、即ち河岸は、マレコン・タラパカ地区というスラム街になっている。河より高い所にある市街はスペインのコロニアル調でそれなりに整っているが、ここには木造の掘建て小屋に屋根は椰子の木の葉で作られた、見るからにボロボロの家が密集している(写真)。雨期の最盛期にはアマゾン河の水位が数メートルも上がるので、それらの家は全て「高床式」になっており、運河と化した水上をカヌーで移動できるらしい。メルカドとその地区とは何箇所かが階段で繋がっており、人がたくさん行き来している。よおく観察すると、さっきから私がおちょくってきた市場の人々は、この地区から来ている人が多いようだ。さっきから階段を下りてこの中を見学したい衝動に駆られながらも、やはり治安上の心配から思い止まっていたが、この市場のおばちゃん達の家なら大丈夫だろうと腹をくくり、愛想を振り撒きながら階段を下りてみる。
 で、そのマレコン・タラパカ地区だが、とっても面白かった。始めは周りを気にしながらおっかなびっくりだったが、街中を板張りの「通路」が縦横無尽に走っており、結構便利にできている(左写真)。勿論、それら全てが高床式であり、足元2mぐらい下には地面(川底)が見えている。汚水をそのまま下に垂れ流していると見えてかなりの異臭を発していたが、我慢して20分ほどゆっくり歩く。こちらから愛想を振り撒いていると、子供達が寄ってくる。デジカメを撮って見せ、文明の畏怖を感じさせる作戦にでる(右写真)。やはり「いい人」は安全なのだ。
で、そのマレコン・タラパカ地区だが、とっても面白かった。始めは周りを気にしながらおっかなびっくりだったが、街中を板張りの「通路」が縦横無尽に走っており、結構便利にできている(左写真)。勿論、それら全てが高床式であり、足元2mぐらい下には地面(川底)が見えている。汚水をそのまま下に垂れ流していると見えてかなりの異臭を発していたが、我慢して20分ほどゆっくり歩く。こちらから愛想を振り撒いていると、子供達が寄ってくる。デジカメを撮って見せ、文明の畏怖を感じさせる作戦にでる(右写真)。やはり「いい人」は安全なのだ。 結局総勢13名が、スペイン人の老夫婦x2+若夫婦、メキシコ人の家族4人、そしてスイス人2人と日本人は私1人ということが解ったのは、アマゾン河を30分ほどボートで下り、支流のシンチクイ川の側にある立派なロッジに着いてランチを食べ終わった頃だった。たまたまそのツアーで一緒になったというスイス人2人は、私よりは数倍ましだろうがスペイン語がそれほど上手くないため、必然的にこの3人は仲良くなり、ガイドとしても英語で話す時はこの3人向けということで、3人が近くに座ることが多くなった。先進国の小国特有の寛容さも備えているこの2人とは、このジャングルツアーを通して非常に仲良くなることができた(写真)。
結局総勢13名が、スペイン人の老夫婦x2+若夫婦、メキシコ人の家族4人、そしてスイス人2人と日本人は私1人ということが解ったのは、アマゾン河を30分ほどボートで下り、支流のシンチクイ川の側にある立派なロッジに着いてランチを食べ終わった頃だった。たまたまそのツアーで一緒になったというスイス人2人は、私よりは数倍ましだろうがスペイン語がそれほど上手くないため、必然的にこの3人は仲良くなり、ガイドとしても英語で話す時はこの3人向けということで、3人が近くに座ることが多くなった。先進国の小国特有の寛容さも備えているこの2人とは、このジャングルツアーを通して非常に仲良くなることができた(写真)。 さて、まずはカヌーで近くに住む部族の村を訪れる。いかにも熱帯雨林の中にありそうな木で出来た高床式の家々に、半分裸族という人々がいた(写真)。まさにウルルン滞在記に出てきそうな環境の中で、彼らの唄を聴き、踊りを見る。ツアーの初っ端から、これは強烈に印象に残った。彼らは吹き矢を実演し、一通りの「儀式」をこなし、最後にお土産の販売が始まった。これは購入する義務はないのだが、子供達がお手製の首飾りや置物を持ってすがって来ると、さすがに冷たくはしづらい。仕方なく首飾りを5ソル(=150円)で買った。イキトスの街中での相場より数倍高い。
さて、まずはカヌーで近くに住む部族の村を訪れる。いかにも熱帯雨林の中にありそうな木で出来た高床式の家々に、半分裸族という人々がいた(写真)。まさにウルルン滞在記に出てきそうな環境の中で、彼らの唄を聴き、踊りを見る。ツアーの初っ端から、これは強烈に印象に残った。彼らは吹き矢を実演し、一通りの「儀式」をこなし、最後にお土産の販売が始まった。これは購入する義務はないのだが、子供達がお手製の首飾りや置物を持ってすがって来ると、さすがに冷たくはしづらい。仕方なく首飾りを5ソル(=150円)で買った。イキトスの街中での相場より数倍高い。 2、3分北上した後、いよいよ最初の地上絵である「鯨」の上を遊覧する。パイロットはご丁寧にも「あれが鯨」と指差してくれたが・・・、すぐには解らない。思ったより小さく、かつはっきりと見えないのだ。その後「宇宙飛行士」、「猿」と続き、かなり慣れてきたがやはり識別しにくい。私はてっきり、飛行機に乗れば誰に言われなくても目の前に大きな地上絵が広がるものと思い込んでいたが、実際にはそうではなかった。その後、有名な「ハチドリ」(写真)、「木」、「オウム」など10以上の地上絵を見て回り、結局40分間程遊覧して元の空港へ戻る。確かに荒野にあのような地上絵が書かれているのは神秘そのものだが、軽く酔ったこともあり、「大感動」というわけにはいかなかった。宿に戻ってデジカメから映像をPCに落として確認してみたが、実際に見た自分でさえ何処に何が写っているのかすぐには解りづらかった。
2、3分北上した後、いよいよ最初の地上絵である「鯨」の上を遊覧する。パイロットはご丁寧にも「あれが鯨」と指差してくれたが・・・、すぐには解らない。思ったより小さく、かつはっきりと見えないのだ。その後「宇宙飛行士」、「猿」と続き、かなり慣れてきたがやはり識別しにくい。私はてっきり、飛行機に乗れば誰に言われなくても目の前に大きな地上絵が広がるものと思い込んでいたが、実際にはそうではなかった。その後、有名な「ハチドリ」(写真)、「木」、「オウム」など10以上の地上絵を見て回り、結局40分間程遊覧して元の空港へ戻る。確かに荒野にあのような地上絵が書かれているのは神秘そのものだが、軽く酔ったこともあり、「大感動」というわけにはいかなかった。宿に戻ってデジカメから映像をPCに落として確認してみたが、実際に見た自分でさえ何処に何が写っているのかすぐには解りづらかった。 ということで、アレキパでは一泊二日になってしまったが、ならばと、もうひとつどうしても行きたかった近郊の「ユーラ」へは確実に行くことにする。アレキパの周りには標高6000m以上の山々が聳えており、富士市もびっくりという絶景(写真)なのだが、その山麓に何と温泉が湧いているのである。ペルーは日本に負けないぐらいの火山国であるため、ここユーラに限らず温泉が湧いているところが多い。オスタルにチェックイン後ランチを食べて、コレクティーボ(ローカルバス)に乗ってユーラ温泉へ向かう。そのコレクティーボは、ご丁寧にも「みなみかしわようちえん」の表示を残した、日本から輸入された中古車だった。
ということで、アレキパでは一泊二日になってしまったが、ならばと、もうひとつどうしても行きたかった近郊の「ユーラ」へは確実に行くことにする。アレキパの周りには標高6000m以上の山々が聳えており、富士市もびっくりという絶景(写真)なのだが、その山麓に何と温泉が湧いているのである。ペルーは日本に負けないぐらいの火山国であるため、ここユーラに限らず温泉が湧いているところが多い。オスタルにチェックイン後ランチを食べて、コレクティーボ(ローカルバス)に乗ってユーラ温泉へ向かう。そのコレクティーボは、ご丁寧にも「みなみかしわようちえん」の表示を残した、日本から輸入された中古車だった。 1時間程経ち、幼稚園児用の小さな椅子にお尻が痛くなって来たところで、こちらが何も言わないのに車掌が降りろという。外国人は私だけで他の乗客は誰も降りないのだが、言う通りに降りてみるとそこは小さな渓谷沿いに緑のオアシスが続くのどかな景色が広がっており、目の前には「オテル・ユーラ」があった。ユーラ温泉についての詳しい情報は「歩き方」に書いてなかったのだが、おっかなびっくりその閑散としたホテルのフロントに行ってみる。何とか温泉に入りたい旨を伝えると、フロントの人の良さそうなオヤジが満面の笑みで温泉のことをひと頻り説明してくれたようだが、スペイン語なのでよく解らない。ともかく5ソル(=150円)の入浴代を払って温泉へ案内してもらう。ちょっとした倉庫のような建物の中に入ると、確かにあるあるお風呂が。本格的な硫黄の臭いが充満している中に、家庭用のお風呂を3つ繋げたような大きさの浴槽が4つある。浴槽といっても深さは1mぐらいあって、プールに入る前の消毒槽と言うイメージか(写真)。家族連れの先客が7,8名いたが、みんな水着で入っている。
1時間程経ち、幼稚園児用の小さな椅子にお尻が痛くなって来たところで、こちらが何も言わないのに車掌が降りろという。外国人は私だけで他の乗客は誰も降りないのだが、言う通りに降りてみるとそこは小さな渓谷沿いに緑のオアシスが続くのどかな景色が広がっており、目の前には「オテル・ユーラ」があった。ユーラ温泉についての詳しい情報は「歩き方」に書いてなかったのだが、おっかなびっくりその閑散としたホテルのフロントに行ってみる。何とか温泉に入りたい旨を伝えると、フロントの人の良さそうなオヤジが満面の笑みで温泉のことをひと頻り説明してくれたようだが、スペイン語なのでよく解らない。ともかく5ソル(=150円)の入浴代を払って温泉へ案内してもらう。ちょっとした倉庫のような建物の中に入ると、確かにあるあるお風呂が。本格的な硫黄の臭いが充満している中に、家庭用のお風呂を3つ繋げたような大きさの浴槽が4つある。浴槽といっても深さは1mぐらいあって、プールに入る前の消毒槽と言うイメージか(写真)。家族連れの先客が7,8名いたが、みんな水着で入っている。 さて、期待に胸を膨らませて温泉に入ってみると、ぬるい!。日本ではこれは温泉とは言わない。もしかしたら、ペルー人用に高温の温泉を水で冷ましているのかもしれないが、外気が20度ぐらいのため始めは寒く感じた。それでも首まで浸かっていると、じわじわと温まってくる。浴槽ごとに泉質も異なるようで、やや白濁した温泉もあった。先客は全てペルー人だったが、面白いことに湯の中で会話が弾むのは万国共通のようである。殆ど通じない中で、延々と1時間ぐらい温泉に浸かりながらスペイン語会話をしてしまった(写真)。大胆にも要約してみると、
さて、期待に胸を膨らませて温泉に入ってみると、ぬるい!。日本ではこれは温泉とは言わない。もしかしたら、ペルー人用に高温の温泉を水で冷ましているのかもしれないが、外気が20度ぐらいのため始めは寒く感じた。それでも首まで浸かっていると、じわじわと温まってくる。浴槽ごとに泉質も異なるようで、やや白濁した温泉もあった。先客は全てペルー人だったが、面白いことに湯の中で会話が弾むのは万国共通のようである。殆ど通じない中で、延々と1時間ぐらい温泉に浸かりながらスペイン語会話をしてしまった(写真)。大胆にも要約してみると、 陸路で国境を越えるというのは、特に日本人にとっては国境を実感できる瞬間であり、楽しいものだ。バスを下りてペルー側の出国手続きを済ます。その後どうしたらいいのか迷っていると、何時の間にか私の周りには同じバスの乗客が二人しかいなくなっていた。ヨーロッパ系のカップルのようだったが、彼らもよく解っておらず、バスに戻ってみてももう他には誰もいない。再度「歩き方」を読み直すと「歩いて国境を越える」と書いてあるので、そのカップルも誘ってそのまま前に進む。すると確かに頭の上には、"Thanks for your visit"というペルー側の看板と、その向こうに"Welcome to Bolivia"というボリビア側の看板があった(写真)。
陸路で国境を越えるというのは、特に日本人にとっては国境を実感できる瞬間であり、楽しいものだ。バスを下りてペルー側の出国手続きを済ます。その後どうしたらいいのか迷っていると、何時の間にか私の周りには同じバスの乗客が二人しかいなくなっていた。ヨーロッパ系のカップルのようだったが、彼らもよく解っておらず、バスに戻ってみてももう他には誰もいない。再度「歩き方」を読み直すと「歩いて国境を越える」と書いてあるので、そのカップルも誘ってそのまま前に進む。すると確かに頭の上には、"Thanks for your visit"というペルー側の看板と、その向こうに"Welcome to Bolivia"というボリビア側の看板があった(写真)。 街の中は「混沌」の世界である。クリスマスイブのため特別だったようだが、人の多さにはとにかく閉口した。道という道に露店が溢れ、朝の山手線もびっくりという具合の混雑振りである。ボロボロの市バスはどれも満員で、車掌が大声で行き先を連呼しながら走っている。侵略者であるスペイン人は、アンデス下ろしの風を避けるべくすり鉢状の盆地に街を造ったため、ラパスでは鉢の底に高層ビルが並び、高級住宅街が位置している。そこから放射状かつ無秩序に坂道が延びており、上に行けば行くほど赤レンガ:アドベで造られた廃墟同然の家並みが広がっている。その光景は遠くから見ると美しく、近くから見ると異様である(写真)。
街の中は「混沌」の世界である。クリスマスイブのため特別だったようだが、人の多さにはとにかく閉口した。道という道に露店が溢れ、朝の山手線もびっくりという具合の混雑振りである。ボロボロの市バスはどれも満員で、車掌が大声で行き先を連呼しながら走っている。侵略者であるスペイン人は、アンデス下ろしの風を避けるべくすり鉢状の盆地に街を造ったため、ラパスでは鉢の底に高層ビルが並び、高級住宅街が位置している。そこから放射状かつ無秩序に坂道が延びており、上に行けば行くほど赤レンガ:アドベで造られた廃墟同然の家並みが広がっている。その光景は遠くから見ると美しく、近くから見ると異様である(写真)。 そんな世界に暮らしている人々は、「民族的」である。ボリビアは先住民族・インディヘナが、人口の55%と南米一の多さを誇る。日に焼けて皺だらけの顔つきをし、三つ編みをして民族衣装を着ているいかにもと言うおばちゃんがペルー以上に多かった。いやがおうにも、ボリビアまでやって来たという実感が強まる。一方、ペルーほど観光化・商業化されていないからか、シャイな人が多く、写真を取らせてくれと頼んでも殆ど断られてしまった。向こうからこちらに話し掛けてくることはまずない。
そんな世界に暮らしている人々は、「民族的」である。ボリビアは先住民族・インディヘナが、人口の55%と南米一の多さを誇る。日に焼けて皺だらけの顔つきをし、三つ編みをして民族衣装を着ているいかにもと言うおばちゃんがペルー以上に多かった。いやがおうにも、ボリビアまでやって来たという実感が強まる。一方、ペルーほど観光化・商業化されていないからか、シャイな人が多く、写真を取らせてくれと頼んでも殆ど断られてしまった。向こうからこちらに話し掛けてくることはまずない。