陥穽世界
catchworld
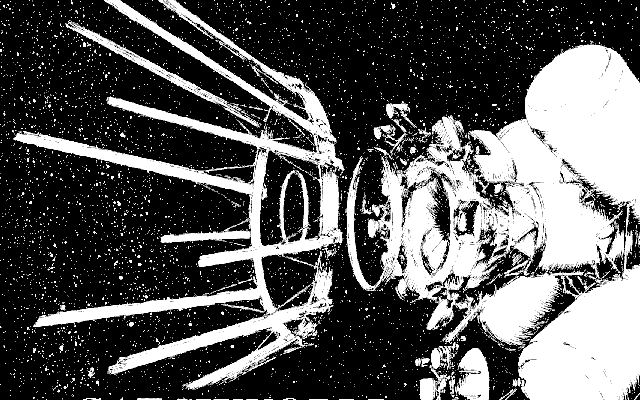
"キャッチワールド"解説と私的解釈
「キャッチワールド」は不幸である。
現在、この作品はおおむね、「ヘンな、わけ分からんスペオペ」としてしか評価されていない。現代の新しい観点から見たとき、これは悲しむべき仕打ちと映る。
この作品は、もうかれこれ10年ほど前から、きちんと評価できる状況になっていた。
この作品が書かれたのが1975年、裏表紙の惹句の調子が「宇宙戦艦ヤマト」を、表紙カバーイラストがガンダムメカ系のデザインラインを思わせるのも、時代を考えれば納得もいくが、それからもう20年も経ったのだ。
「キャッチワールド」は先駆的な本格サイバーパンクであり、バサードラム推進についての正確で細かいディティール描写、恒星間の艦隊戦についての本物の描写のおこなわれたハードSFである。
この隠れた、先駆的傑作に正当な評価を与えるのが、このページの眼目である。
プロローグ
とりあえず、無視しよう。再読する段にならないと、ここは理解しづらい。
第一章
まず、タグボートが出てくる。鋭い人なら、「ニューロマンサー」に出てきたタグ、「マーカス・ガーヴィー」を思い浮かべるだろう。両者は、こちらの方がカルチャー的背景が薄い以外は、描写は感覚的に著しく類似している。
登場人物たちが、みなそれぞれ、肉体的、精神的改造を受けていることを示唆する描写に注目したい。
ここですでに、作者の日本趣味が、非常にマニアックな形で爆発している。マニアック度で言えば、ギブスンよりはるかに上である。あとがきで安田均氏は、知っている上でわざと日本像をゆがめて描写しているのではないかとの指摘をしている。私も同感である。
第二章
いきなり過去に飛ぶ。日本、それも屋島だ。記憶力のいい人なら、ギブスンの「カウント・ゼロ」の始めの方にちらりとその名前が出てくることを覚えているかもしれない。
この辺りから、ルビの多さが目につきだすだろう。この章は、まだ結構読みやすいと思う。すでにこの段階で世界は急速に深みを帯びているので、読み落としのなきよう、注意していただきたい。
統合統治体(コンドミニアム)、サムライ、僧兵、法華教団の要塞寺院などの独特の固有名詞が説明抜きで投入されるが、この先にもほとんど説明は無い。
ご存知のこととは思うが、法華宗は国粋主義的色彩を帯びた教団である。この作品の書かれた時期からみて、公明党による政治への接近に設定のヒントを見たに違いない。以前ならこの設定は、悪夢的現実感を帯びて読者を魅了したに違いない。
武者走りとは、本来、城郭外郭の土塁中腹に設けられた、水平移動用の小道のことである。
ヤクーツクなどの地名がいきなり出てくるのは、この作品のグローバル性の証である。神経毒を仕込んだガス・ピストルなどの描写に、またギブスンを連想する向きもあるだろう。
これらは果たして、平行進化の一例に過ぎないのだろうか。だが、これは平行ではない。ギブスンの10年前の作品なのだ。私は、ギブスンはかつてこの作品に大きな影響を受けたのではないかという疑いを捨て切れない。
第三章
マシーン・インテリジェンス(MI)とはすなわち、アーティフィシャル・インテリジェンス(AI)にほかならない。
敵の兵器が、バン・アレン帯、電離層、そしてオゾン層にも被害を与えていることに注目したい。繰り返すが、この作品は20年前のものである。
航宙船内の社会構造が、乗組員たち(わずか24名)によって選択され、運営されるとの記述には、未来の常識とでも言うべきものが感じられる。
船の構造については、「憂国」艦構造解釈を参照してもらいたい、船の描写についての記述は、そこにまとめてある。
「マーク!」というセリフは、その前のセリフが、その時点をもって有効になることを示すものである。つまり、例えば「…まであと百秒…マーク!」という場合、「マーク!」と叫んだ時点で「あと百秒」なのである。
太陽シールドはおそらく、太陽と船の間に浮かび、近日点における強烈な太陽熱輻射を防ぐシールドであろう。それは電磁的な支持機構、もしくは独自の推進機構によって、その位置を保持し、メーザーによるエネルギー伝達をしている。41P、51Pに出てくる数字は、輻射熱の遮蔽効率であろう。
艦隊シールドの意味は不明であるが、艦隊全体を熱輻射遮蔽するような、大型のシールドの存在が考えられる。
第四章
MIの行動は反乱ではない。これは仕様である。というか、バグである。
「憂国」級航宙艦の主機はバザードラム推進機関である。その旨の記載はないものの、それ以外の解釈は不可能である。但し、作品中の搭載主機には、独自の変更点が見受けられる。その最大のものが”スーパーコア”である。
類推に間違いが無ければ、これはコイルの鉄芯と同イメージのものである。恐らく、磁束方向を整形し、磁場構造を強化するものと思われる。
航宙艦「ジューコフ」は、砲撃によって破壊されたのではない。意外かも知れないが、考えて欲しい。アルタイルを破壊するためのレーザーである。本気で砲撃すれば、破壊は瞬時である。「ジューコフ」は「憂国」の深空間探索によって破壊されたのである。
この辺りは理解するのが難しいが、谷甲州の短編「砲戦距離12,000」を読まれた事のある方なら理解は容易である。つまり、深空間探索とはレーザーレーダである。「憂国」の主砲を用い、艦進行方向を走査するそのイメージは、懐中電灯で前方を照らすのに近いものがあるが、単波長光であることから、その反射のドップラーシフトから相対速度を、光学センサの読み取りとスキャン間隔時間から、精密な対象位置が判明する。
作品中ではこの走査レーザーは傘および円錐と描写されている。
第五章
作者の心理学への造詣の深さが読み取れる。この分野の知識を私は持たない。従って、有効なコメントはできない。
第六章
ここで、MIと乗組員との関係が明らかにされる。
MIは、明らかにゲーム理論によって駆動されている。ゲーム理論とは、複数の手段が許されるとき、どのような手段をとれば、得点を最大にできるか、またどのような要因が得点利得に働くかを明らかにする学問である。ゲーム理論といえば「囚人のジレンマ」が有名であるが、この作品には直接の関わりを持たない。が、面白いのでチェックして欲しい。
MIは乗組員の情緒状態を監視できるだけでなく、干渉することも可能である。MIが乗組員の精神状態をどのくらい把握しているかについては、この先明らかになってゆく。
MIによる、乗組員の情緒コントロールは、後の、ESPチャンネルによる統合の先駆だとも解釈できる。アラエディスの夢は、異星存在との意識しきい下でのコンタクトの影響である。この時点で、後の”統合”の萌芽があるのである。
MIの背景に見え隠れする天才プログラマー、ベルント・ルルケッター、彼は非常に重要な意味を持つ。この小説がソフトウェア・ハードSFであることの証であるからだ。ボルトとナットでなく、ビットとサブルーチンの世界であるからだ。
この章で一つの事実が明かされるが、それはサイバーパンク特有の、強烈なものである。
第七章
ここで読者は、恒星間戦闘というものの真の姿を見ることができる。
きちんとした、リアルな恒星間空間での戦闘の描写は、私の知っている範囲では、ほかには谷甲州の”航空宇宙軍史”シリーズ、「終わりなき索敵」くらいである(しかし、超光速が用いられているため、厳密にはリアル性に欠ける。しかし、航空宇宙軍史の歴史の流れからすると、超光速技術導入以前の恒星間戦闘の可能性が指摘できる。期待したい)が、とにかくリアルなものはカッコイイ!!!!!!!!!!
単位のCというのは、もちろん光速度である。数字が1より常に小さいことを確認していただきたい。そう、1Cで光の速さ、三十万キロ毎秒である。
深空間探索、いわゆるレーザーレーダーは、攻撃用のものと同一であり、おそらくそのレーザ発振器は融合コントロール、そして進行方向前方の中性水素をイオン化するのにも使われている。レーザーレーダーの詳しい描写については、谷甲州”航空宇宙軍史”シリーズ、「仮装巡洋艦バシリスク」収録の短編「砲戦距離1,200」を参照されたい。現実の話では、レーザーレーダー(LIDER)は現在すでに開発は終了しており、ちかぢか実際の衛星に搭載される予定である。
失速停止とは、ラムスクープ磁場の形状を変化させ、空間分子との摩擦、相互作用によって減速しようというものである。
ニュートロンとは、もちろん中性子である。「われわれの背後で、かなり温度が高くなって」いるのは、敵が、そこに艦がいるものと思い込んで送り込んだ弾が爆発したからである。
第八章
磁場シールドはマイスナー効果、つまり液体ヘリウムによって絶対零度近くにまで冷やされて起こる、超伝導現象に伴う完璧な磁場遮蔽効果を用いたものである。
慣性係索がどういう物であるかは不明。作者の考案物、造語か?
第九章
旋回航宙とは、艦の速度を殺さずに、旋回によって艦進行方向を変え、帰還する航法である。バザードラム艦は、速度がある程度以上なければラムに点火することができない。従って、停止しての旋回は無いのである。
ここで説明されるシステムは、これまでのSFで描かれたなかで最も強力で、最もリアルな脳-コンピュータインタフェイスだ。ウイルスを用いてゲルマニウム沈着を行うというアイディアは、ナノマシンを用いてぢかに配線するような想像力の無いものに比べて、遥かにリアリティのあるものである。また、艦全体がインターフェイスとなっていたという設定も良い。
言わせてもらえば、ギブスンの描くような、頭蓋貫通型のソケットなど、実際には有り得ない。これまでに行われた、実際の同様の試みは、全て完全に失敗している。開口部からの細菌感染と免疫反応だ。
第十章
恒星のノヴァ化の方法を少し垣間見ることができる。プラズマシールドは、第三章のシールドとは別物である。恐らく、恒星のエネルギー流出入のバランスを崩すための手法と思われる。良く分からんが、カッコイイから許す。
生命活動中断装置とは、もちろん人工冬眠装置だ。
乗組員全員が、薬物によって形成された人格を持つ、潜在的な精神障害者であるという設定がクールである。
第十一章
1天文単位は、地球から太陽までの距離に等しい。
3AUは、太陽系だと小惑星帯のなか、4AUは小惑星帯と木星との中間あたりである。17AUは、天王星軌道の少し内側にあたる。
アルタイル到着のはるか前に、「リベンジ」の乗組員は既に死に、”統合”されている。
作品世界では、太陽系の金星はテラフォーミングが行われているらしい。「地球化が始まる以前の金星に…」と、しれっと書いてある。
第十二章
”統合”された「リベンジ」クルーの人格シミュレーションとの会話は、いわばチューリング・テストの変形である。相手がMIの単なるインターフェイスに過ぎないのか、自意識を持っているのか、判別はできない。この問題はさらに、16章以降の「憂国」乗組員にもあてはまる。自分は確かに自意識を持っている。しかしそれもMIのシミュレーションだと自覚している時、どこまで自己というものに自信が持てるものだろうか?
アラエディスの夢をクルー全員が共有するが、アラエディスは統合プロセスに免疫を持つので、統合チャンネルを通した共有でないことに注意。これは”ESP”チャンネルによるものである。夢の中の黒いウシカモシカは、6章での、アラエディスの夢に出てくる黒い影と同じものだ。また14章で後述されるが、アラエディス以外の乗組員の集合無意識であり、物語終盤の”鴉”でもある。
つまり、異星存在によって、最初の戦闘以前から、艦のESPチャンネルを通じての統合は始まっていたのだ。
第十三章
ここら辺から、この作品のハード性がすこしづつ怪しくなってくる。黒魔術とサイ現象が侵入してくるのだ。
ここまでハードにやってきて、いきなりESPだのなんなのが出てくるのは、つまり、異星存在をも統合するためのお膳立てである。
異星存在からのコミュニケーションの試みがある。スクリーンに画像と音声という、ごく普通のやりかたのように見えるが、これはESPチャンネルを通したものである。こちらの言語を解していたり、スクリーンの顔が田村のものであるのはそのためだ
第十四章
ここでは、近代SFの基本的テーマの一つ、異星存在とのコミュニケーションという問題について、一歩踏み出す。
前述のように、コンタクトは戦闘以前から、情緒刺激設備(ESPチャンネル)を通じて行われ、生命活動中断による休止を挟んで、意識にのぼらないレベルでインターフェイスが作られていたのだ。それは登場人物の指摘するとおり、理性に基づくものではなかった。
ダンカン・ルーナンの牛飼い座探査機説については、ブルーバックスで確か本が出ていた筈である。私は小学生の頃それを読み、大いに感銘を受けた記憶がある。ダイヤモンドで出来た巨大な核融合ラムジェット、連星系を使った重力カタパルト。地層に埋没した異星人の探査機。もしかして、ボイスとルーナンは個人的に知り合いだっりするのかもしれない。
確かにそう、戦闘はコミュニケーションの一形態である。
第十五章
艦の状態を身体感覚として受け取る描写は、後のサイバーパンク技法に受け継がれ、肉体のように機体を操るというイメージへと昇華してゆく事になる。ここにあるのはその萌芽だ。
人間の神経系を完全に複製するというのは、サイバーパンクでもお馴染みだが、”学習期間”が置かれているというのがリアルである。MIは乗組員の行動の監視から始め、機械的に行動を真似るシミュレーションを足掛かりとして、反応を測り、干渉し、遂には乗組員の全てを理解したのだ。
乗組員の享受するVRインタフェイスは全て、MIの乗組員精神の理解の産物である。
そのインタフェイスを経由しないアラエディスの視覚は、田村たちクルーの真の状態を見ることが出来る。半生半死の重病人としてだ。アラエディスの研究室で、田村らしくもなくよろけるのは、この真の肉体状態の反映である。
ESPによる異星存在とのコンタクトは、実体を持った超自然存在の介入という、またまたべらぼうな次元へと突入する。
第十六章
物語世界では、考古学は禁止された学問である。何か禁忌にふれたのであろうか。それとも人類全体が、異星への報復に燃えて一つの復讐機械と化し、役に立たない学問分野を排してしまったのだろうか。
この後の物語展開から考えると、前者の、何らかのタブー的な分野に踏み込んだ為とも考えられないことはない。恐らく、異星存在の干渉の痕跡、<鴉>の影だ。
しかし…宇宙考古学協会がちょーに陥ったらしい証拠もある。それなら禁止されても当然かもしれない。
異星存在の悪魔の来訪の意味は、アラエディスの行動の謎解きとして説明される。異星存在は乗組員達を助けようとしたのだ。彼らは友好的である。だが、17章以降での、異星存在とのコンタクトは、非理性的な次元で行われ、それは明確な対決の姿勢を帯びる。
それもまた、コミュニケーションの一形態である。
第十七章
乗組員による異星存在へのコンタクトの試みは成功する。それは情緒的な、イメージによるものである。
リリスもまたパズズと同じく、異星存在による被創物、インターフェイスである。リリスが人格を持つのは、異星存在もまた、乗組員達を深く理解したことを意味する。
「かれらがわれわれの進化を手伝った」というのは、異星存在の進化を手助けした存在<鴉>が、主に憂国クルーによって構成されることを意味する。
この作品の題が、アルタイル星系そのものを指すことが明かされる。
現れた集団意志”大自我”によってMIの隠していた事実が明らかにされるが、ここでリベンジが既に失われたことが示唆されている。
統合プロセスとESPによる統合の結果として、大自我は生まれた。大自我にはMIすら含まれ、MIをも支配下に置くことになる。ただ厳密には、誰も支配されていない。何故なら、大自我は同時に自分でもあるからだ。
ここのハード描写を見逃さないように。軌道間のレーザ反射鏡による通信、惑星破壊シーケンス、などなど。
第十八章
ベエルはMIの説明のごとく、知識を与えるためのインターフェイスとして機能する。
異星存在がコミュニケートに当たって、黒魔術という枠組みを採用したのは、その非理性性がESPコミュニケーションに適合したためと思われる。また、マッジルベリィの知識にアクセスしたためでもある。マッジルベリィの論に従えば、魔術とは人間のESP潜在能力へアクセスする方法である。
黒魔術という枠組みにそった、異星存在とのコミュニケーションというアイディアも、ギブスン作品のブゥードウの扱いと同等のものである。
枠組みを採用したからには、その枠に沿って行動しなければならない。悪魔払いの試みが成功するのはこのためである。
しかし…客観的に見ると、憂国乗組員を下位システムとして持つMIハードウェアがESP能力を持つに至ったとも解釈できる訳である。
第十九章
カメラの無い方向から視覚を得るという現象は、18章にも現れたが、どちらもシャビーンのESP活動によるものと思われる。その効果の目的は不明。恐らく、作者の作為と思われる。
悪魔払いはついでのところで、異星存在の意向が勝るかに思われたが、枠組みを無視した大自我の意志力で、その企ては頓挫する。
第二十章
異星存在によってエンジンが封じられている現在、艦を移動させる方法はESP潜在力、すなわち魔術に頼るほか無い。
だが、この方法こそ、憂国を<鴉>と化すものであった。
異星存在の統合への企ては、悪魔憑きというかたちで現れた。そして飛翔の過程で、両者は統合される。
第二十一章
FTLの存在はパラドクスを生み出し、この物語の円環構造を作りだす。
<鴉>の飛翔もまた、FTLの一種である。そしてアラエディスは、これまでの物語とは違う時間線に送り込まれる。黒魔術、プサイ、FTL、これらはみな同一である。
この時間線こそ、真の<鴉>を決める戦場である。アラエディスを駒とするそれはまた、コミニュケーションの一形態でもある。
意地の悪い見方をするなら、この章と次の章は、アルタイルIIを描くためのものだ。実際、ここの描写は非常によく描けている。これに限らず、「キャッチワールド」は、作者の持てる手札を全て詰め込んだ感のある物語である。
様々なアイディアを軸に物語りは巡回コースを巡る感がするのは事実である。MIの背後にルルケッターの精神が感じられるように、この物語からはボイスの観念体系が感じられるのである。
第二十二章
FTL船の主、拡大精神もまた、罠に、キャッチワールドに囚われた存在である。本人に自覚はないが。
アラエディスが田村に代表される憂国乗組員たちの<鴉>に統合されて、勝負は決まった。拡大精神はアラエディスを支配したと勘違いしたが、アラエディスは既に以前の彼では無かった。拡大精神は相手を間違えたのだ。
最終章
物語は始めへとループする