「ガルガンチュアIII侵攻」
galganture III
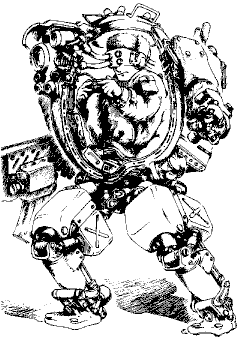
「ガルガンチュアIII侵攻」
不意に、背中に冷たさ。
その予期せぬ感覚に、大尉は声をあげた。ジョイパッドを取り落とす。
「ひっ」
ゴーグルを剥ぎ取る。狭いカプセルは赤のEL照明で薄暗く、ボリュームを探し、もっと明るくしようと思うが、肘は突っかえ、しまいに空気清浄器の、フィルターの金属の角にしたたか打ちつけ、あざを造ってしまう。
膝を抱えたばかげた姿勢で、今日はもう7時間。
ドラム缶と大差ない狭さの<シェル>。折り畳んだ足は、しびれて感覚を失い、もう二度と立ち上がれそうにない。背筋の痛みは悪夢だ。
背伸びのように両手を頭上に挙げ、そしてさっきの冷たさの原因を知った。
ハッチの縁、パッキンが濡れている。
衛星地表降下からもう半年。
侵攻は、予定をはるかに越え、すでに泥沼化の兆候を見せていた。
『この三百年間、我々人類は、営々として宇宙へと進出し、敵対的な世界に対して勝利してきました。先人の英雄的な献身に対して、我々は限りなき感謝を捧げるものであります。
ですが、この勝利は束の間のもの、そして敗北の始まりでありました。
人類は、遥かな星々にまで旅し、想像することもできぬほど遠い惑星で社会を、文明を築くようになりました。
それは確かに勝利です。ですが、その社会は、われわれ太陽系人の想像を越えた、恐るべきものとなりました。
プロクシマ、バーナード、そしてウォルフ359。これら星々で人類は分裂の危機に瀕しているのです。
人類の分裂がこのまま見過ごされれば、その結果は不幸なものとなるでしょう。
我々は、人類統一の使命を担わなければならないのです。
皆さん、戦争は終わり、太陽系は一つとなりました。
今度は、星々を一つとする番なのです』
−協定世界暦2264年1月3日、L5議政院コロニー内
第12スタジオ(アドレスID:DSL2240,GFN3314)
での、イ・ウォンバク経団連第一書記の演説より抜粋−
第二次太陽系戦争の終結後、肥大した軍産複合体、そして不景気による支持率低下に悩む政策団体は、状況を打開すべく、外星系侵略を計画した。
22世紀初頭からの植民によって、半径15光年以内の17の星系に、人類はその活動拠点を築くまでになっていた。巨大な複合ラムシップは、一握りの人々を遥かな果てへと送り出し、送り出しつづけた。
太陽系内で交わされる通信量に比べて、外星系と太陽系とのそれはあまりに細く、遅く、結果として外星系には独自の文化が生まれていた。
例えばプロクシマ。衛星ガリケニーのデータ植民者たちの、数億のワンチップAIに混交し作りあげた仮想社会。
ロス154の、家族単位で所有する宇宙船がまるで昆虫のように交接し、繁殖する社会。
そして、バーナード星系。木星の4倍の大きさのガス巨星を巡る衛星上で栄えるバイオテク社会。
それら、異様な外星系社会(そして文化)に対する民衆の嫌悪を煽るのは簡単なことだった。
大戦中に、軍事テクノロジーは長足の進歩を遂げていた。
全長二千メートル、1天文単位の距離から精密爆撃可能なテラジュール・マスドライバ。恐るべき生産能力を保証する自己増殖パッケージ。半世紀前に予言されたバークストラン理論は、遂に、超光速跳躍機関として結実した。
マイクロブラックホールの周囲、歪んだ時空は”まっすぐな円環”を作り出す。
無限の長さを持つ線形加速器であるそこで、重粒子は光速へと、限りなく加速される。その過程で粒子情報は、カー・ブラックホールを通して過去へ繰り込まれ、有限時間内にエネルギーは、リトルバンを起こすに足るものとなるのだ。
そして、
大戦中の悪夢を結晶化した戦闘艦「鄭和」「李舜臣」「東郷」は跳躍した。
艦の情報は量子数に翻訳され、誕生したミニ宇宙の中で、情報幾何学的変換をうけ、再び別の座標に翻訳される。
バーナード星系に。
「シェルターの仮設が出来ました」
少尉が報告した。
しとつく雨と霧、マングローブ雲霧林の気根と泥濘の中に、シェルター・ポッドは設営されていた。
「わかった。小隊長たちに報告の準備をさせておけ」
少尉の外観は、大尉のシェルスレイブと全く同じだった。さらに、大尉の戦術顧問として、それ相応の高度な知的能力を備えていた。
ちくしょう。大尉は思った。奴は俺より遥かに有能だ。自分が大尉である理由は、ただ一つでしかない。人間だからだ。
ポッドの内部のメインテナンス、環境整備と気圧調整が済むまで、いらいらしながら1分弱、そしてハッチを押し上げる。ハッチは湿り気を帯びていた。
ポッドの中はお世辞にも広いとは言えない。が、シェルに比べれば天使の幻が見えそうなほどに天国だ。足を伸ばし、背伸びをする。以前は柔軟体操もしていたが、最近ではやる気も起こらない。
ポッドの冷蔵庫にビールがあったのは半年前の話だ。その頃は、この戦争は楽勝だろうと思っていたものだ。
飲む水にはわずかに異臭があった。原因が再生処理システムだとすると、かなり困ったことになる。それはシステムの死の前兆である。
しかし、これが外部からの影響だとすれば最悪だ。衛星植民者は、バイオテクではどうやらこちらの1枚上であり、生物学的汚染は致命的なものとなることを覚悟しなければならない。
チャンネルを開く。右手のモニタに少尉の合成映像が映る。
「報告準備できました」
正面スクリーンに、泥の中に無気味に直立しするスケルトン達が映った。頭蓋に挿したプラグから、相互に同軸光ファイバが伸びるのを見た。
大尉はマットの上にあぐらをかくと、言った。
「報告しろ」
スクリーンに彩色された立体グラフが描かれた。いかにも有能そうな声で、少尉の合成顔が解説してゆく。
部隊の戦闘能力、行動能力は確実に低下していた。
低下率さえ加速していた。自己修復が追い付いていない。永久損傷が部隊のロボット達を蝕みはじめていた。
「原因は粘菌類似体による侵食と磨耗です」
「”ネバネバ”か?」
「はい。新種がまた確認されています」
「除去はできているか」
「いいえ。この状況下で、除去のために精密マニピュレータを用いることは得策ではないでしょう。それに、マニピュレータは不具合が多くなってきています」
大尉はため息をついた。
「対策を述べよ」
「特に目新しいものはありません。不要行動の禁止と関節自由度の制限、そして早期のメインテナンスです」
「そのようなだな……ちくしょう。」
背筋に鈍い痛み。
少尉はAIであり、人間の肉体的な側面については全く理解しない。だが、結構冗談を解するいい奴だ。話し相手になりそうな奴は、少尉だけだった。
大隊には、人間は彼一人。
その下に、大尉のシェルスレイブにそっくりな外観を持つ、AIの少尉。
階級では軍曹になる、戦術エキスパートシステムを積んだ重兵装スケルトンが6体。それに従軍するスケルトンが40体。
そしてモンキーと呼ばれる武装ロボットが120体。
歩哨マシンや偵察ハードウェア、工作ロボットや補修サーボは使い捨て同然、無数だ。
程度の差こそあれ、すべて人工知能マシンだ。
大尉はたった一人、おもちゃの兵隊を率いて東へと向かっていた。
その衛星に、住民たちはボゴタと命名していた。
侵攻方針には、相手の文化を踏みにじることが暗黙の了解として含まれていたから、太陽系軍は、衛星を惑星ガルガンチュアの三番目の衛星、すなわちガルガンチュアIIIと呼んだ。もっとも、侵攻後しばらくして、ガルガンチュアIが、住民の軌道コンビナートであることが判明したのだが。
衛星の赤道半径およそ2800キロ。太陽系最大の衛星タイタンより大きく、火星よりわずかに小さい。
衛星は惑星に近すぎた。地球の月のように潮汐力で固定され、その面がそっぽを向くことは永遠に許されなかった。
赤い(植物の赤だ!)地表のあちこちに、クレーターの環状の稜線があった。長波長光を効率よく吸収すべく改良され、不毛の大地に百年かけて根付いた植生が、衛星地表のほぼ半分を覆っていた。明らかにクレーターの跡とわかる、小さな海が点在していた。
AI強行探査機は、衛星地表を強力なレーダーで走査し、撃墜されるまでにこれら様々な情報を送ってきた。その情報が役立った。植生は極地を覆っていなかった。
そしてあと一ヶ所、ガス巨星の真下、そこでは、主星の弱々しい陽光はガルガンチュアの地平線に遮られ、朝晩のわずかな時間を除くと、光はほとんど無かった。そこは冷たい赤道だった。
そこに大規模な人工構築物が確認された。大気の擾乱から、静止軌道を越え一直線に伸びる、ごく細いワイヤの存在が推測された。軌道エレベータは、最大の戦略目標だった。
0.2マイクロメートルからデカメートルまでの電磁波長域でほぼ不可視の揚陸ポッド16隻が、巨大なガルガンチュアとその衛星の狭間に分け入るようにして、<目>へと降下した。構築物は、その異様な形からそう呼ばれていた。
背景放射を偽装しながら16隻は大気圏に突入し、ある艦は制圧兵装カプセルを、またある艦はなめらかな先行爆撃弾を4波に分けて放出した。空力形状をした制空機動体が、タイタン防空戦の有名なフォーメーションを取った。大気摩擦の熱がすでに侵攻者の位置を暴露したはずだった。
だが、迎撃してくるミサイルは無かった。電磁加速ペレットも、防空機動兵器も無かった。
知性化機甲8個師団(あるいは人間128名と機械たち)は、無抵抗の敵拠点を占拠した。無人だった。住民はいなかった。
彼らはどこへ行ったのか。
誰もまだ、そのささやかな、大掛かりな罠に気付いていなかった。
皆まだ、制圧侵攻は2週間以内に完了すると信じていた。
「こんなものあったか?」
大尉は、少尉に尋ねた。
「さあ……、この手の代物を歩哨AIは予期していませんでした。非常に微妙な変化であるため、重要度を低く見積もったのでしょう」
木の葉や小動物にいちいち警報を出していては、歩哨はつとまらない。
「そこらへんが、低レベルAIに見張りを任せることの問題点だな。知能をいたずらに高くしても、今度は退屈したりサボったり。お前だって、退屈な時があるだろ」
「私等AIは寝ませんから、大尉が休まれているなど、退屈でしかたがありません。でも、だからといって、歩哨なんて嫌ですよ。そんなのは士官の任務じゃありません」
「お前、俺が寝てる時は何してるんだ?」
「小説を読んだり、文章を書いています。この戦争の記録をしようと思いまして。
人工知性の視点からの戦争ってやつを」「そりゃ楽しみだな。出来たら読ませてくれ」
「太陽系に戻ったら、その時はぜひ第一号の読者をお願いします」
「戻れたら……か」
そこで、息をつき、ため息をし、そしてしばらくして
「さて、これをどう思う?」
歩哨AIが見逃すはずだった。促成の巨木の樹皮にびっしりと生えた、ぬるぬるするコケを、ナメクジがかじった痕のように見えた。
まさにそのとおりで、真夜中(この衛星の昼は5日間つづく。それとは別に、人間の生理に合わせた24時間体制が、環境の明るさに関係なく用いられていた)、巨大な灰色のナメクジが、その辺りを這っていたのが記録されていた。
だが、その痕は、こうも読めた。
”君達の侵略は失敗した。諦めよ”筆記体の北京語インピン・ローマ字だった。
「連中の言うとおりかもしれんな」
一行が行軍を開始してしばらくして、大尉は少尉に赤外線で囁いた。
「連中とは、あのメッセージを書いた連中のことですか?」
大尉は、パワードスーツ乗りには決して与えられることのない特権、どこでも好きな所を掻けるという特典を行使していた。とりわけ腹のあたりをボリボリ掻きながら答える。
「住民達が、密林の樹冠に住み着いて、ほとんどテクノロジー無しの生活をしていることは判っている。ほかの事は、あんまり判っていないがな。
住処は木のうろや、枝の根元に架けた葉っぱの家。機械といえば、信じられないほど粗末な織機。信じられるか?連中は、樹皮や昆虫分泌物で作った糸を、一本一本、手で織り込んでいたんだ。
なら、どうやってあんな、ナメクジをあやつったり、細菌をばらまいたり、低空飛行を阻害する蜘蛛の糸やら、人間そっくりの赤外反応をばらまくカエルやら、その他いろいろ、そんな具合でどうやったらできるんだ?
どこかに秘密のバイオラボでも持っているなら、もうとっくに見つかっているはずだと思わないか。
それなら、誰があのメッセージを?
……謎ばかり。泥の中。こんな具合で、勝てる見込みなんて無いんだよ。大体、何に勝とうというんだ。木のぼりして、猿みたいに逃げ足の速い原住民を追い回すのか。
畜生、政治家どもが言ってた、危険な外星系異常文化はどこなんだ?」
苦い声だ。
「考えられる可能性としては、2つあります」
その事はすでに考えていたのか、人工知能戦略指導体にのみに与えられる特権情報が示唆したのか、少尉はよどみなく答えた。
「ひとつは、原住民が自分達のテクノロジーを、みごと完全に隠蔽しているというものです。どうやったらそんなことが出来るかは判りませんが。
もう一つは、何か別の要素が介入している、というものです。恐らくは衛星の外で、ステルスな軌道ラボで制作した生物要素を、どのような方法によってか、我々の封鎖網をかいくぐって投入しているのでしょう。
この可能性には、いくつかの穴、例えば我々の行動に対する要素出現のスピードの速さを説明できませんが、いくつかの仮定により、すべて説明が可能です。
司令部では、その線で探索をしているようです」
「で、司令部は、どのくらい探索しているんだ?」
「5ヶ月間、です」
「ふむ」
右翼樹冠を進む歩哨が、通信プローブがやってくるのを発見した。
プローブは長さおよそ1メートル、環境色を偽装するステルス表面の有翼機だった。2重反転ローターで推進され、部隊の発した指向ビームで向きを変え、上空を過航しながら、紫外線波長のレーザーで情報を送ってよこした。
太陽系軍は、傍受と通信の混乱を最高に警戒していた。だから、必要度の低い情報や生活情報、娯楽情報は小さな通信プローブで、送ってよこしていた。最近では何でも、最高位の機密までプローブで送ってきた。
内容は要約すれば、早く帰ってこい、だな。大尉はそう判断した。
「回収収容要求は却下されたようです」
「それでいて早く帰ってこい、とはな。勝手なもんだ」
「全くです。……ところで、帰って、何をするんでしょう」
「さてな……。案外、軌道上に引き上げるんじゃないかな。でもってどこかから小惑星でも引いてきて、AI兵器を量産して、数にものをいわせて制圧しようって腹、だったりすると助かるんだがな」
「だといいですね」
気付いた時には遅かった。
部隊は展開し、精緻な作戦シミュレーションは走り出し、AIのROMに焼かれ、あらゆる資源が再配置された後だった。
拠点は最初の上陸地点である<目>に設けられ、大規模戦略知性が軌道上から降ろされた。降下した人員は300名近くにも及んだ。<目>の構築物の巨大さが、探索器材と人員をいたずらに消費させた。
構築物の探査は一ヶ月に渡って続いた。構造物の正体が、蟻塚の一種であることが判明し、さらに、現地民の生活の痕跡が全く無いことが確認されるまで。
AIも気付かなかった。AI統合体のヒエラルキーは、過去の実績によって学習、重みづけされている。過去の固定概念に縛られたAIが主導権を握り、相手が既知の戦略ドクトリンに従っているものと、疑っていなかった。
どんな暗黒も、軌道に反射鏡に展開すれば解決するはずだった。そこが現地民の活動の拠点なら、それが無ければおかしかった。
もし、太陽系艦隊がやってくる前に反射鏡を片付けたのだとしても、植生にははっきり痕跡が残るはずだった。そんな痕跡はなかった。反射鏡ははじめから無かった。
さらに、連中は紛らわしい構造物を作る白蟻を飼い、貴重な軌道エレベーターをおとりとして餌に供したのだ。
侵略者はその拠点を、ただ寒い、環境劣悪な土地に固定させられた。しかも、そこへの降下補給に必要なエネルギーは最大だった。補給船の軌道は、摂動と重力異常と、分厚い上層大気の影響で大きく揺らいだ。
AIは大急ぎで、罠の土地を再探査した。上陸時に急いで行われた中性子探査にひっかからないような熱核時限爆弾でも無いとも限らない。一面に仕掛けられた、充分に放射線シールドを施された原始的な熱核兵器が、太陽系の兵隊たちを熱いプラズマにする。そんな幻視に戦略知性たちは脅えた。
もしかすると、反物質爆弾かもしれない。放射能スキャンに引っ掛からない反物質兵器は、太陽系では先だっての戦争で大量に使用されていた。外星系には製造出来るような技術力も設備もエネルギーも無いはずだが……
人員は大急ぎで軌道上へと待避させられた。その混乱のあいだに、44人もの人命が事故で失われた。その中には中佐が2人、大佐と少将が1人づつ含まれていた。
機器の故障はやたらと多く、奇妙にも故障率はさらに増大しているようだった。
気密シールは劣化し、ナノマシン・ポンプは処理能力を軒並み落とした。降下連絡艇の耐熱 外皮は、いつの間にか危険なまでに強度を落としていた。カビだった。細菌だった。奇妙な共生地衣類類似体だった。自己増殖する微小兵器、バイオ系ナノマシンによる破壊工作だった。
人員の間に、未知の皮膚疾患が蔓延していた。感染者は代謝低下処理を施され、速やかに隔離された。
気がついた時には、小型の熱核兵器が与えるものに匹敵する損害を、太陽系軍は受けていた。損害は続いていた。
対策は常に受け身となった。静かに攻撃を加えてくる生物種は目まぐるしく変動していた。消耗率はどのような予想をも、最大規模の交戦状態を予想したものをも上回った。
自分達の拠点を囲む蟻塚の、白蟻達の高度な情報処理能力、広範囲で徹底的な情報収拾能力にAIたちが気がつくのは、まだしばらく後のことだった。
ハメられた。
そんな感じが、いつもしている。中でも、軍隊には騙された。
カッコイイはずであった。正義と人類の未来のためにシェルスレイブを駆り、そして彼は将校、英雄のはずであった。
産まれてこのかたずっと、千もの電子の宮廷道化師たち、細心の注意を払って彼を見守り、人格を育て、喜ばせ、幸せにしつづけるAIたちにかしずかれた、王侯の暮らしをし、それを当然としていた。
軍隊は違う。それに喜びはなかった。不条理だった。
腰の痛みが、つらい。
まあ、以前から、自分は騙されているとは感じてはいた。
AI達は自分を暖かい羊膜でくるみ、真実にフィルターをかけていた。
軍隊という、大掛かりで間抜けな嘘付きに付き合って、それがはっきりと判った。
真実は不条理で、痛く、寂しいのだ。
ついさっき、少尉が自爆した。
現地民の改造種の中には、深いクソ穴を掘る昆虫がいる。深さは平均して5メートル、径は1メートルほどもある穴をわざわざ掘って、そこにいちいち糞をしにくるのだ。
この衛星を覆う促成マングローブの巨木たちは、たいていそこに根を発している。
現地民が種を蒔いていったのか、とにかく糞穴は最高の苗床となった。栄養豊富で暖かで常に湿った穴の中で植物は育ち、みるまにこの衛星を覆ったのだ。
そして糞穴は簡単に落とし穴にもなる。現地民は小枝と落ち葉でカモフラージュしていた。巨木の根を踏み越えての走破では、おのずと足元の超音波探査もおろそかになる。
少尉は、目の前で見事にズボッとはまった。少尉の機体が糞の中に完全に没するまで5分ほどあった。引き上げようとするのを少尉は制した。「帰還命令は絶対です。一秒でも早く行かなくては。引き揚げに間に合わなかったらどうするのです?
たかが機械、器材の回収などに手間取っている時ではありません」
「しかしおまえ……」
「チャンネルを開いてください。戦略情報を転送します」
結局、彼は言うとおりにした。助けたところで、作戦が終われば、少尉の個性はリセットされてしまうのだ。
少尉は自爆した。蓄電コイルの冷却効率を低下させ、超伝導を壊したのだ。回転するフライホイールに棒きれを突っ込むようなものだ。貯えられていた膨大な電力は、コイルに突然出現した電気抵抗により、爆発的に熱に変換された。
アーマーたちの背中に糞が飛び散った。
転送されてきた情報の中には、長いテキストファイルが混じっていた。ハイパーリンクされたそれは、少尉の小説だった。
話し相手を失った大尉は、シェルの操縦をAIに任せ、それに読みふけった。
部隊は無言のまま、東へと歩みつづけた。
意外だったが、少尉の文章は下手だった。何でも上手にこなした少尉にしては妙にこなれない文体で、長々と綴られていた。
率直な内容だった。人間にはとても真似のできない率直さで、おのれが運命、敗北の予兆、この作戦の軍事的意味の空虚さ、部隊の壊滅、そして大尉、彼の運命についてメガバイトが費やされていた。
小説とリンクされた戦略情報は、太陽系軍が事実上敗北したことを告げていた。
衛星全域を制圧しておきながら、当初の目的、危険テクノロジーからの人民と環境の開放(すなわち外星系文化の抑圧)を達成できず、ただいたずらに消耗するばかりであり、その有り様は、大規模交戦のあとの敗軍を思わせた。あらゆる機材を残して、太陽系軍は退却することになるだろう。AIたちは衛星地表に残り、反乱の防止と治安維持、現地民の教導と、あらゆる任務を負うことになるが、消耗したメカ達に成果を期待している訳ではなかった。AIたちは見捨てられるのだ。
大尉達人間の運命は、それに比べれば幾分ましだろうと思われた。少尉は、バーナード派遣艦隊の将員全員、誰も故郷のエアロックをくぐれないだろうと予測していた。恐らく全員が隔離される。ガルガンチュアIII生物種の恐ろしさは、実際以上に評価され、将員全員の死後、隔離コロニーは真空滅菌されるだろう。
太陽系にたどり着くまでに死んでいなければ、の話だが。
手の甲にきつい痛みを覚えた。
ゴーグルを剥ぐ。
手の甲には、爪でかきむしった赤い筋が縦横無尽についていた。血がにじんでいる。
そして、圧倒的なかゆみを自覚してしまった。腹といい背中といい、無意識のうちに掻きむしりまわった痕が、じんじんと感じられた。2本の腕では足りない。
上着を脱ぎ、シャツを剥ぎ、皮膚から血がにじむのを自覚しながらかきむしり、気付かなきゃ良かったなどと考え、そして、原因に思い当たったが、気が狂いそうなかゆみの前では、どうでもいいことだった。ハッチの劣化したパッキンから、また水滴が背中に落ちた。
そうしてしばらくして、かゆさより掻きむしった後の痛みのほうがひどくなって、そんな状態で一息ついた。
苦痛がかゆみを圧倒してくれた御陰で、やっと冷静さが戻ってきた。苦痛なら制御できる。
血だらけの身体は、赤い照明のおかげでどす黒く見える。痛みに突っ張る皮膚を意識しつつ、ゆっくりとシェルスレイブとの連結を取り戻す。
見回すと、一人だった。
そして、連中がやってきた。抵抗する気はなかったが、相手のために何かをしてやる気もなかった。
チップAIの敵接近警告がうるさい。突然、寒くなる。そして光。何本もの腕。
顔に何か、恐らくマスクが押しあてられる。目の前に、細い針のついた透明なチューブがある。液体か何かが入っている。突然、大尉は恐怖にかられた。
だが、針は彼の腕に突き立てられ、眠りへと落ちてゆく。
気付けば自分は、見知らぬ言語で喋っている。
(ラテンイングリッシュです)と、すかさず埋めこみ知性が答える。翻訳はこいつの担当だ。「……この糞食らい共、この水虫野郎共、なめくじ野郎共……」
「太陽系の人間は、みんなあんたみたいなのかね?」
ざっくり織られたシャツを来た髭面男が聞いてくる。「俺をどうするつもりだ?」
髭面男はため息をついた。
「……まあいいや。聞いとくれ。
太陽系の連中はみんな引き上げたよ。あんたは置き去りだ」
なんとなく理解してしまいそうな心の一部に悲鳴を上げる。埋めこみ医療モニタが心拍数の増大を警告する。埋めこみ知性がドラッグを分泌処方したが、それもただ、この状態の異様な雰囲気を増幅するばかり。
そだを編んだ壁、草葺きの暗い小屋。天井の梁に、発光体が蠢いている。よく見ればそれは気味悪く大きな虫の群れだ。
腕に差し込まれたチューブに気がつく。
「こ……これは何だ。外せ……外せよ……外せ!」
「暴れなさんな。お前さん、点滴も知らんのかね。ほら、これでも嗅いで落ち着きな」
「……もう充分落ち着いとるよ。その怪しいブツは引っ込めな」
髭面男の説明は、ここの住民の技術レベルの低さの説明でもあった。しかし、
「かゆみはまだ感じるかね」
かゆみはきれいさっぱり消えていた。が、皮膚の感触がおかしい。
戦闘衣の袖をまくりあげてみる。白っぽいペーストが一面に塗りたくられていた。
「いま君の皮膚に移植中の細菌は、ここで暮らす上で絶対必要なものだ。そいつが厚い脂質を分泌して、君を寒さから護ってくれる」
髭面男は続けた。
「鼻がムズムズしないかね?決してほじっちゃいけないぜ。鼻孔上皮細胞を更新中だからね。他にも肺の中にたっぷり寄生細菌を移植してあるし、腸内にもだ。
その御陰で、二酸化炭素たっぷり、メタン臭い空気を好きなだけ呼吸できるし、食い物も大丈夫、感謝するんだぞ」現況の変化は理解の能力を超えていた。髭面男は立ち上がる。
「腹減ってないか?なんか消化の良いものを持ってきてやる。点滴は外すなよ」
説明は、驚異だった。
「俺達は、新しい腕を作ったのさ」
髭面男と、もう一人は若い女性。白い服を着ている。来るなり髭面と激しいキス。そのあからさまな皮膚接触の有り様にたじろぐ。
「ヒトは道具を作る腕を持ったことによって、新しい進化の地平を開いた。我々の持つ腕は、古い腕とはまったく次元がちがうもので、だから俺達は、新しい進化の道を歩んでいるんだ」
にっこり笑って舌を突き出す。
「へっへっへ」
隣の女性が笑って、髭面の背中を叩く。
「俺達の口の中は、目いっぱい改造されているのさ。お前さんらは、分子を感じることができるかい?分子をばらすことが?分子を組み立てることが?
俺達は素手でできるのさ。
酵素が俺達の腕なのさ」
彼らは、一人一人が二十四時間フル操業のバイオラボなのだ。
見えない、ミクロの腕で生態系を織りなし、生物種を生み、化学物質で会話するのだ。連中の接吻は会話も同様なのだ。
秘密の暗号を記した化学物質が衛星を巡り、太陽系の部隊毎に担当を決めた現地民たちは、気の赴くままにオーダーメイドの攻撃生物種をばら撒くのだ。
敗北は当然だった。
数日後、大尉は貰った上着を着込み、滑り止めの付いたサンダルを穿いて、樹冠の村を散歩していた。
珍しく雨もやんで、高い空には深い青の晴れ間さえ見えていた。
一本天に突き出した大枝に、子供達が群がっていた。こちらに気付き、ささやきを交わす。やがて、一人降りてきて、
「おっちゃん、太陽系の兵隊さん、なんやろ?上がってこんね」
子供達の腕に助けられ、樹海の地平線を見通す高さに登る。
「ねえ、おっちゃん、生まれはどこ?」
「地球って、人間がうじゃうじゃ居るんでしょ?んなの臭くない?」
「おっちゃん頭に電気の配線埋めてるって聞いたけど?」
子供達の質問に答え、太陽系の風物を物語るのは、心の奥にある不安をひとときでも忘れさせてくれた。星々の驚異に子供達は目を輝やかせた。
夕日はいつまでたっても沈まず、それは妙な気分だった。惑星ガルガンチュアは地平線の下で、星はちらちらと薄い雲の間から見えていた。「あれ、流れ星流れ星!」
子供が指差す方向には、白い航跡が薄く見えた。
「お前等しがみつけ!!」
大尉は叫んで樹にしがみついた。子供達はきょとんとしていたが、おずおずと枝にしがみついていく。それを見て冷静になり、衝撃波がたどり着くまでまだかなり時間があることに気がついた。
「もういいから、降りろ、早く降りろ。降りて、安全な、頑丈なところに引っ込め」
「なんでや」「早くしろ!」
大尉は恐ろしい剣幕で怒鳴った。
「砲撃だ。全員に触れてまわれ!」
そして今度は、流星が素早く天を横切るのを見た。砲撃が開始されたのだ。
一人残った高枝の上に腰をおろし、軍隊内では有名な禁テクで、埋めこみ知性にドラッグの分泌を命じた。落ち着いた気分で、すべての終焉を見届けようと思った。
少尉は予言していた。最も忌むべき終焉が来ることを。最悪の犯罪が侵されることを。ひとつの世紀にわたる人類の血と汗が、土塊に還元されることを。
人類世界最強の戦闘艦、鄭和級の主砲、テラジュール・マスドライバは、100キログラムの岩塊を光速度の1パーセントという恐るべき速度にまで、一瞬にして加速する。それに艦の巡航速度が加算されれば……
3艦共が砲撃に参加しているとすれば、射撃間隔は……一つ見逃したか、そしてもうすぐ……
流星と言うより、短い光の槍だ。次のそれは一瞬、地面に突き刺さる様に見えた。
もう近い。向こうの空が赤いのは、夕焼けではない。
衝撃波が見えた。
小さな衛星の未来がかき消されるところを目撃しながら、太陽系も、また人類にも未来はないことを確信しつつ……
大尉は吹き飛んだ。